ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination
People / ハンセン病に向き合う人びと

日本のハンセン病療養所では、子どもを産み育てることは禁じられていましたが、
戦後の宮古南静園では多くの夫婦が、それぞれに葛藤を抱えながら子どもをつくりました。
現在、南静園でボランティアガイドをつとめる知念正勝さんもそんな一人。
隔離政策の現実を目の当たりにし、理不尽な差別・偏見にあいながらも、
「ハンセン病は治る」という希望と、「社会に出るべきだ」という信念をあきらめることなく持ち続け、
「自分の手で子どもを育てたい」という一心で、不自由な体を押してさまざまな仕事を経験し、
自分の足で歩みつづけてきたのです。
Profile

知念 正勝氏
(ちねん まさかつ)
1932(昭和7)年、沖縄の離島・水納島(現在沖縄県宮古郡多良間村)に生まれる。1951(昭和26)年、18歳のときに宮古南静園に入る。園内で結婚し、子どもが生まれたことを機に、1965(昭和40)年に社会復帰。土木建築をはじめさまざまな仕事を経験する。現在、南静園退所者の会の代表として、ボランティアガイドをつとめるほか、さまざまな啓発活動にたずさわっている。

そうです。私は昭和40年に園を出ました。園内で結婚して、子どもができて、その子を自分たちの手で育てるために、社会に出たんです。
園にいる者同士が結婚するときは、断種・堕胎するということが条件になっていましたし、あのころは入所者たちのほとんども、「園内で産むことができないのは当たり前だ」と考えていました。それでも子どもが欲しいと強く思う人もいるし、結婚が認められなくて夫婦寮には行けなくても、同棲生活をしているうちに妊娠するということもあるわけです。なかには親元に帰って産むという人たちもいましたが、私たちは親を頼ることができなかったので、家内が妊娠したときは、産むか産まないか、ずいぶん悩みました。「産んだほうがいい」とは誰も言ってくれませんからね。二人で話し合った末に、産もうという決断をしたんです。
でも家内のお腹が大きくなってくると、やはり周囲の目が気になるし、いやな空気もあって、だんだん家内は耐えられなくなってしまったようです。私に黙って堕胎手術に応じようとしたんですが、幸いにもというか、失敗してしまった。それを知った私は「絶対にだめだ」と反対して手術を止めさせました。そうして、娘が生まれたんです。ただし子どもを産むことはできても、自分たちの手元に置くことはできない。置いておけるのは、1歳の誕生日までという条件があったんです。私もそれだけは忠実に守らなければならないと思ってました。

私と同じ年代の人で、10組近くの夫婦が子どもを産んでいたと思います。一人子どもを産むと、夫のほうはほとんどみんなワゼクトミー(断種手術)を受けるので、二人目、三人目をもつことはできませんでした。なかには、二~三人も子どもをつくった夫婦もいましたが、それは生まれた子どもをぜんぶ預かってくれるだけの、実家との関係がよほどがっちりしている人たちでしたね。
私の生まれは水納島(みんなじま)と言って、沖縄県内でも離島中の離島と言われる小さい島、生活が苦しいので島民がみんな宮古島に移住してくるようなところでした。私の母もそうやって大変な思いをしていた。だから生まれた子どもを母に預けるわけにはいかなかったし、やはりなんとしても、自分の子どもを自分で育てたいという思いがあった。
たまたまそのころ私は南静園の護岸工事の手伝いをしていたんですが、その現場責任者の方が、護岸工事が終わってもずっと一緒に働かないかと誘ってくれたのです。私にしてみれば、それこそ渡りに船でした。それで思い切って園を出て社会復帰することにしました。
ご覧のとおり、私は手が不自由ですからね。できる仕事が限られてしまう。8年ほど土木関係の仕事をして、そのあとは新聞社などの集金業をしたりしました。お客さんから、床の上にお金を投げるように置かれて、それを拾うのに大変な思いをしたとか、嫌な思いもいろいろしました。でも、そんなことにいちいち悩んでいるわけにはいかない。なんとしてでも生きていこう、子どもを育てよう、人が笑おうが何を言おうが、そんなことは気にしないという思いで生きてきましたね。

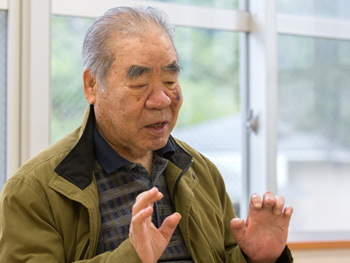
いちばん辛かったのは、一軒家を借りることになって、そろそろ引っ越そうと思い、行ってみると大家さんのおばあちゃんが待っていて、一枚のドル貨幣(復帰前の沖縄で流通していたドル貨幣)を床の上にぽんと置いて、「この家はあんたがたには貸せません。これで我慢してください」と言われたんです。あえてなぜかは言わなかったですが、むちゃくちゃに腹がたちましたよ。その時、家は自分でつくろうと決意しました。しかし、そうは言ったものの、土地も金もありません。
それで以前工事現場でお世話になった棟梁に、相談したんです。すると「まず土地を借りろ」と。そうすれば家をつくる材料は自分が材木店に掛け合ってなんとかしてくれると言うので、言われたとおりにしました。そうやって、ほんの十坪ほどですが、親子三人で暮らすための家を自分で建てたんです。
「なんとしても家がほしい」とずっと思っていましたからね。アパートに住むとか他人の家に間借りするといったことは、窮屈というか、どうしても嫌だった。家族水入らずで暮らせるところがどうしても欲しいと思って働いていましたから。
いい出会いもいろいろありました。工事現場の仕事をしていたとき、休憩になるとみんなでバケツに入れた水を柄杓で飲み合っていたんですが、私はどうしてもそれができなかった。みんなが飲み終わったあと、一人こっそり水を飲むというようにしていました。あるとき親方が現場に来て、水を飲みながら「知念、お前も水を飲みなさい」って言って、柄杓を私に差しだしたんです。これにものすごく勇気づけられましたね。踏ん切りがついた。「ぼくもみんなと同じでいいんだ」と思えるようになったんです。
その方には、もうひとつびっくりさせられたことがありました。何年かその会社で働くうちに、棟梁級の先輩たちがみんな別の会社に行ってしまった時期があったんですが、親方から「知念、今日からお前が現場責任者だ」と突然言われたんです。でもぼくは図面の見方も知らないし、測量機器の扱い方もわからない、使える道具はノコギリとゲンノウだけ。だから「それはだめです、できません」と言ったんです。それでも「自分が教えるからやりなさい」と、親方から言われました。
なんとか自分なりに図面の見方なんかも、理屈だけはいちおう理解して、責任者としてやることになりました。他にも人はいるのに、なぜあのとき親方はあえて私を責任者にしたのか、聞いておけばよかったなあと思います。もう亡くなってしまったんですが、本当にお世話になりましたね。ただ世話になっただけじゃなくて、こういうことを通して、社会で生きていくための勇気を与えてもらいました。

宮古南静園の正門。施設はこの先の急な坂を降りたところにある。かつては三方を崖に囲まれた谷底のような場所だった。
そこは自分でいうのも何なんですが(笑)、現場で働く皆さんが、意外と私を慕ってくれて、私の言うことになんでも協力してくれたんです。そのへんを親方も見てくれてたのかなと思います。
その会社は、その後いくつかの建設会社が合併して、いまは大きな会社になっています。会社がどんどん大きくなっていくなかで、これはもう自分は付いていけないと思ったので、やめさせてもらいました。そのときも「土木責任者としてがんばってくれ」と言われたんですが、ぼくのようにビクビクしながら生きてきた人間にできるわけがないと思ったので、「ありがたいけど、やめさせてください」とお願いしました。でもそこまで私をたててくれた人がいたということは、人生のなかで大きな出来事だったと思います。
土木のつぎに就いた仕事が新聞の集金、次は電気料の集金とOHK(復帰前の沖縄放送協会)の集金。それから「宮古スキンクリニック」という、沖縄らい予防協会の支部の仕事もやりました(註:沖縄ではハンセン病の外来診療所がつくられた)。私の妹は「兄さんは、仕事が切れてもすぐ翌日には別な仕事についている。ふつうは仕事をやめると次の仕事を探すのは大変でしょう」って不思議がってましたが、それはもう、家族のために一日たりとも仕事を切らしてはだめだと思って必死だったからです。大変でしたが、そうやっていろんな仕事を経験することも、社会のなかに入って行くのに役立ったと思います。

とくに日ごろから何か言ってきたということはありませんが、娘はいま家族訴訟の宮古原告団の共同代表をしていますよ。きっと親の苦労も、少しはわかってくれてるんじゃないかと思います。
それと娘の子どもが二人いるんですが、つい最近、とつぜん夜の10時にその一人から電話がかかってきましてね。私は孫たちにもとくに詳しい話をしたことなかったんですが、家族訴訟のニュースかなんかを見て、電話をくれたらしいんです。私がいま南静園でボランティアガイドをしていることも関心をもってくれてたようで、「自分はおじいさんがやってることをすばらしいと思う。だから自分もいろんなところで、ハンセン病の話が出たときは自分なりにみんなを啓発するつもりで話をしているんだよ」って言ってくれました。「ああ、わかってくれてたんだな」ってうれしくなりましたよ。

南静園の浜辺から荒波を望む知念さん。この浜には戦時中に入所者が見舞われた過酷な体験の記憶が眠っている。

昭和初期の寺子屋式の学校「八重菱学園」、戦後になって琉球政府によってつくられた。「稲沖小中学校」など、園内学校の歴史を伝える「学び舎の碑」

南静園の将来構想の一環として整備が進んでいる人権啓発交流センターとハンセン病歴史資料館。知念さんはここでボランティアガイドを務めている。

歴史資料館に展示されている、昭和初期の患者住宅の復元模型。
1951(昭和26)年、18歳のときに来ました。でも、すぐに治ってここを出られるだろうと思っていました。というのも、宮古市内の病院で診察を受けたとき、「いまはプロミンといういい薬があって、治る病気になっている。だから療養所に入って治療しなさい」と医者が言うのを聞いていたんです。父親は、薬だけもらって家で治療できるような方法を教えてくれと言ったんですが、「規則があるからそれはできない」と言われました。
「らい療養所」といえば、みんなものすごく嫌がっていたし、ぼくもいま資料館に展示してあるような、粗末な小屋にうずくまるようにして患者たちが療養しているところといったイメージがあった。でも、「治る」という言葉を聞いたから、何年かかっても治るのならいいじゃないかと思ってここへ来たんですね。実際に来てみてびっくりしました。赤い瓦屋根の建物が並んでいて、ものすごくきれいなところだったから(笑)。入所者たちも元気に野球やバレーボールをやっているし、「ここはなんだ」と思った。
療養所に来てから一カ月くらいたったとき、一人の方が退園したんです。トラックを2、3台も借りて荷物を積んで、坂をあがって門を出ていくのを、キリスト教の讃美歌――「また逢う日まで」みたいな感じの歌をみんなで歌いながら見送ったんです。それを見ながら友人に「俺もちゃんと治して、ああやって出ていくぞ」と言ったら、「おまえはバカか。ここに入ったら二度と家に帰れないことを知らないのか」と。「でもあの人はああやって帰っていくじゃないか」と言ったら、「あの人は特別なんだ」と言われました。「病気を治して家に帰るんだ」という私の夢がいっぺんに壊されてしまったんです。
そのあと、昭和31年に、沖縄の二園に派遣されていた田尻(敢)というハンセン病の専門医の講演を聞いたんです。そのときに「らい病」ではなく「ハンセン病」という言葉とともに、ノルウェーのハンセンが病原菌を発見したことや、いまではプロミンからDDSという薬に切り替えられていることなんかも知りました。だからますますハンセン病は完全に治ると信じたし、治っても療養所にいないといけないということがおかしいんだとも思うようになりました。「ここにいるのは不自然だ。出るのが当たり前だ」って決めていた。そういうこともあって、昭和40年に思い切って退所することができたんです。
私は病気のせいで義務教育を受けられなかったんですね。新制中学ができて一学期だけ出たんですが、手の指が曲がってくるし足の裏にもケガばかりするという状況になって、学校に行かなくなってしまった。それで昭和29年に南静園に琉球政府立の小中学校(稲沖小中学校)ができると聞いて、真っ先に手をあげて入らせてもらいました。おかげで少しはまともに読み書きができるようになりました。
学校を出たあとは、自治会の仕事をするようになりました。そのころの南静園は、新しい病棟ができて施設がよくなりつつあったのに、入所者の待遇は以前と変わらないままだった。入所者が亡くなると、園がやってくれるのは「ご臨終です」といって死亡を確認するところまで。そのあとの火葬や葬儀のいっさいは、ぜんぶ自分たちでやっていたんです。そういう状況を変えたいということで、自治会が「生活改善運動」を始めて、琉球政府に訴えるとか、活動がものすごく活発になっていたんです。
もちろん、偏見のないすばらしい先生たちもいました。とくに戦後になって医大を出た若い医者たちが、少しずつ変化も起こしてくれたと思います。ぼくはバレーボールをやっていたんですが、実際にこんなことを目にしました。そのころは職員と入所者がいっしょにバレーを楽しむことはありましたが、水を飲むときだけは分けられていた。コートの両サイドに、入所者用の水、職員用の水がそれぞれバケツで置かれて、やっぱり柄杓で回し飲みをしていた。そうしたら、当時の園長の中村先生が、入所者用のバケツから水を飲もうとしたんです。入所者がびっくりして「先生、それうちらの水だよー」って止めようとしたら、先生は平気な顔で水を飲んで「それがどうした」って(笑)。その日から、他の職員たちも入所者のバケツから水を飲むようになったんですよ。

職員宿舎の塀に残る弾痕。1944(昭和19)年の10・10宮古初空襲のときに被弾した。

南静園を一望することができる高台に、1942(昭和17)年につくられた監視所の遺構が残っている。
残念ながら、その先生がいなくなったあとに、また揺り戻しがあったんですけどね。しばらく新しい園長が来ない時期があって、そこにきた民間医が「我こそは“らい予防法”を絶対守る」という考え方の人だったんです。南静園の初期の歴史のなかで、朝鮮の小鹿島(ソロクト)の療養所から転勤してきた園長(多田景義氏)が、それまでの家坂園長の開放的な方針を変えて、三方の丘に鉄条網を張り巡らせたり、見張り所や監禁室をつくったりしたんですが、まるでその時代に戻ってしまったかのようなことをやろうとしたんです。園のまわりに鉄条網を張って、裏道を遮断して穴を掘って通れないようにするとか。その穴の跡がいまでも残っていますよ。
そういうこともあって、私にとって南静園での日々は、闘いの日々でもありましたね。愛楽園にくらべて南静園の自治会運動は激しかったと言われてますが、本当にその通りでした。琉球政府の厚生部長をしていた医者が、「もう二度と南静園には医者はよこさない、医者をよこしてもみんなケンカして追い出すから」って言ってたこともあったそうです。
サラ、コラ、デラというアメリカ風の名前が付けられた三つの台風がありました(註:宮古第一台風=サラが1959年、第二台風=コラが1966年、第三台風=デラが1968年、いずれも宮古島に甚大な被害をもたらした)。
最初の台風のときに南静園も建物がほとんど壊れて、木造をやめてスラブ(鉄筋コンクリート製)に変えたんですが、それが第二台風でまた被害を受けた。スラブの独身寮の廊下がぜんぶ吹き飛ばされたりしました。第三台風のときは、私の家内が風で吹き飛ばされて、あわやということがありました。街路樹にひっかかったおかげでなんとか生き延びたんです。それくらい大変な台風でしたよ。
ここであったことをいろいろと知って、それが当たり前のことだったと思うか、当たり前ではなかったと思うか、よく考えてほしいというふうに言います。それと、やっぱりハンセン病について正しいことを知ってほしいと思うんですね。みんなが正しい知識をもっていれば、差別や偏見や、それによるいろんな被害が起こることもなかったと思うんです。こういうことが二度と繰り返されないためにも、正しい知識をもって、それぞれに考えてみてほしいということを、なんとかお伝えしようとしていますね。
取材・編集:太田香保 / 撮影:川本聖哉