ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination
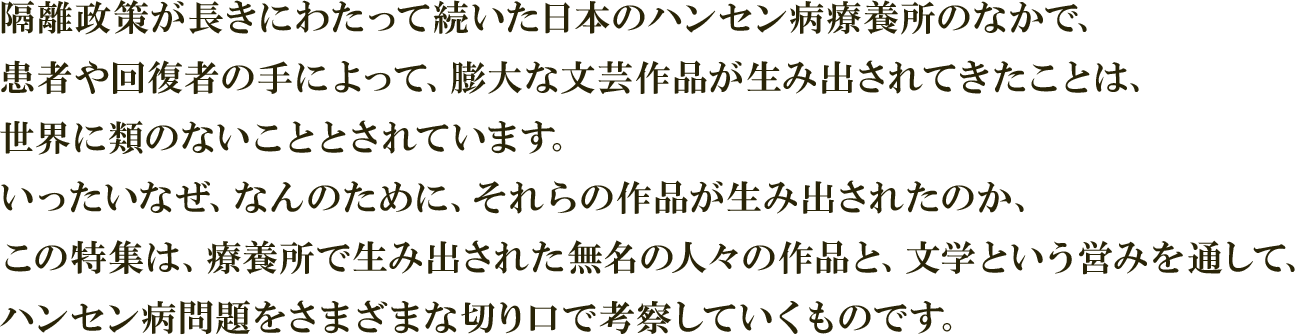

佐藤 健太
日本では1909年の連合府県立癩療養所設立以来、多くの文芸作品が書かれ、
いまもハンセン病者(本連載では元患者・回復者もふくめてこのように表記する)の手になる著作が刊行されつづけている。
日本以外の国ではこのような傾向は見られないとよく言われるが、ではなぜ日本のハンセン病者たちは、
隔離された過酷な状況下にもかかわらず言葉を紡ぎつづけてきたのだろうか。
ハンセン病にかかわるようになって20年以上が過ぎても、この問いは未消化のまま沈殿してゆき、
より大きな問いとなりわたしをとらえて離さない。
同人雑誌『火山地帯』の主宰者で、ハンセン病違憲国家賠償請求訴訟の原告でもあった島比呂志は、
文学とは「宛名のない手紙」であると規定した。
小説、詩、随筆、評論などを書きつづけ30年以上を経た段階でも島は、
軽々しく「文学」という言葉を使うことにためらいを覚えてきたという。
なぜなら「文学とは何か」という問いに答えられない自分を知っていたからであった。
「しかし最近、文豪夏目漱石にして長年「文学とは何か」の答えを求めて苦悩したことを知って、
いささか愁眉をひらいた。
漱石は「自己本位」と解したらしいが、わたしはいつごろからか、
「手紙」それも「宛名のない手紙」だと思いつき、苦しまぎれの答えとするようになった。」
(島比呂志「書くということ」『片居からの解放 ハンセン病療養所からのメッセージ』社会評論社、1985年、10ページ)
島は「苦しまぎれの答え」と謙遜しているが、ハンセン病療養所における文芸活動を考えるうえで、
島の文学観は大きな示唆を与えてくれる。療養所における書き手たちの執筆動機は多様であると思われるが、
膨大に遺された作品群をいずれも「宛名のない手紙」と解することは格別おかしなことではないだろう。
「(前略)このように古い本や雑誌までが大切にされ、図書館はもとより個人までが保存に心がけるとなると、
わたしのような者が書いたものでも、あるいは死後にまで残るのかも知れない。
そしてわたしの肉体はもう存在しないというのに、わたしは読者に語りかけ、読者の共感を呼び、
そこに人間と人間の魂の触れ合いが実現するかも知れないのである。」
(前掲島『片居からの解放』13ページ)
島が期待した「人間と人間の魂の触れ合い」は、しかし、作品が読み継がれなければ成立しないのは言うまでもない。
多磨全生園の山下道輔、長島愛生園の宇佐美治、双見美智子ら各氏によって、
療養所の文芸作品、機関誌をふくめた関連資料は収集され守られてきた歴史がある。
入所者の高齢化により当事者の語り部活動が困難になりつつある今日、
遺された「宛名のない手紙」をハンセン病問題に関心を寄せるそれぞれが読み継いでいくことは、
「ハンセン病問題の継承」という営みのひとつのあり方と言っていいだろう。
膨大に遺された作品群のごく一部を紹介することしかできないが、
この連載が、わたしの見知らぬだれかが「宛名のない手紙」を読むきっかけとなれば、
筆者としてこれに勝るよろこびはない。

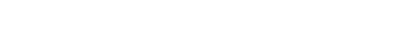
大学1年生のときに佐藤真監督のドキュメンタリー映画『阿賀に生きる』を観て水俣病問題と関わるようになり、病と社会の関係に興味をもつ。大学院で群馬県の草津温泉にあったハンセン病者の集落「湯之沢部落」の研究に取り組む。大学院修了後、皓星社に入社し、ハンセン病に関する書籍を数点担当。現在、フリーで出版の営業や編集をするかたわら、東京と静岡を拠点に「ハンセン病文学読書会」を主宰している。共編著に『ハンセン病文学読書会のすすめ』(2015、非売品)、共著に『ハンセン病 日本と世界』(工作舎、2016)がある。『ハンセン病文学読書会のすすめ』『ハンセン病を学ぶためのブックガイド』(工作舎、2016、非売品)をご希望の方は下記のメールアドレスにご連絡ください。
sbenzo.jokyouju■gmail.com(連絡先:佐藤健太)※■を@に変換してください
2017.6.22
2017.11.28
2017.11.28
2017.11.28