ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination
People / ハンセン病に向き合う人びと
※本記事に記載の肩書き・内容は取材当時のものです。
フィリピン・マニラの南西320km、パラワン州の北部に位置するクリオン島。
かつて1930年代には7000人近いハンセン病者を収容し、世界最大の隔離島として知られた。
アメリカの科学知と人種主義にもとづく規律権力と、
それに抗い、自分たちの尊厳ある生を全うしようとする島の住民の戦いの歴史があった。
政治学者の日下渉さんは、極限状態の中でより善き生を追い求めたクリオンの人々の姿に
正義とは、秩序とは、愛とは何かを考える糸口があるという。
クリオン島の知られざる規律と抵抗の歴史を日下さんにうかがった。
Profile

日下渉氏
(くさか わたる)
1977年埼玉県生まれ。名古屋大学大学院国際開発研究科 准教授。大学生時代にワークキャンプ活動を通じてフィリピンの人びとの優しさに魅了されて以来、フィリピンを主な対象に政治学を研究。人びとが分断や序列を乗り越えて相互的に織り成す共同性や社会秩序をアナキズムの視点から研究する。主な著書に、『反市民の政治学─フィリピンの民主主義と道徳』(法政大学出版会、2013年、大平正芳記念賞、発展途上国研究奨励賞)、『承認欲望の社会変革─ワークキャンプにみる若者の連帯技法』(共編著、京都大学出版会、2015年)、『フィリピンを知るための64章』(共編著、明石書店、2016年)。


戦前のクリオン島
クリオン島が生まれた理由は、大きく2つあります。
1つは近代科学の発展です。ハンセン病の原因をめぐって遺伝説と感染説がありましたが、1874年に「らい菌」が発見されました。ハンセン病が感染するということがわかり、科学者たちがハンセン病者の強制隔離を提唱するようになります。
アメリカは、ハワイのモロカイ療養所や、本国のルイジアナ州カーヴィルで隔離を実施します。ただ、ハワイの研究所は予算難ですぐに閉鎖されますし、本国では自分たちの国民なので実験的治療を強制できなかった。他方、植民地のフィリピンでは、多くの予算が投入され、徹底した強制隔離と実験的な治療が活発に行なわれました。
もう1つの理由は、アメリカの植民地主義です。アメリカは、非西洋の「未開人」に「自由」と「民主主義」を与えて文明化させるとして、植民地主義を正当化しました。それは、ある意味フィリピンだけでなく、戦後の日本も同様です。そうして自分たちと同じ文明の高みに包摂する、つまり「恩恵的同化」させる。これがアメリカの「愛」だというのです。
フィリピンに派遣されたアメリカ人の保健衛生行政官は、ハンセン病者はもっとも社会から疎外されているがゆえにもっとも「愛」に飢えていて、アメリカの「文明化」に従順だと考えたのです。それを主導したのは、軍医出身のビクター・ハイザー保健局長官です。彼は、ハンセン病者の隔離、治療、そして病の根絶を、病者への「恩恵」と信じました。1904年にクリオン島を購入し、もともとの住民を隣島に移し、公衆衛生予算の三分の一も費やして、この事業を進めていきます。

かつてこの港から隔離された人びとはクリオンに上陸した

クリオンで亡くなった人びとの墓地
ハイザー長官は、1906年からフィリピン各地にいたハンセン病者をクリオン島に強制隔離していきます。それまで彼らは自由に暮らしたし、家族と一緒にいたのに、急に島に連行されるわけですから、強く抵抗しました。家族は病者を隠しましたし、保健衛生官との暴力的な衝突も相次ぎました。ハイザーらは、フィリピン人が隔離に抵抗するのは、未開と迷信にとらわれて、アメリカの愛と科学的治療の意義を理解しないからだと考えました。
ハンセン病がスティグマ化されたのは、国家が介入してハンセン病が恐ろしい病だと喧伝してからです。そういう面では日本の「無らい県運動」と同じですね。
クリオン島は、1909年には1700人以上の病者を収容する療養所となります。ハイザーは、これでほぼ全病者の隔離を終えたという宣言をします。あとは島にいる病者が死ぬまで面倒をみさえすれば、フィリピンのハンセン病を克服できるというのです。
しかし、その後もフィリピン各地で続々とハンセン病者が見つかり、クリオンの人口はどんどん膨れ上がり、1935年には約7000人近くにもなります。「世界最大の療養所」となったのは、アメリカの目論見をはるかに越えてしまった結果だったのです。
しかも1930年代の世界恐慌によって予算が逼迫し、クリオンの事業にフィリピンからだけでなく、アメリカからも批判が集ります。そこで徹底隔離の方針を変えて、1ヵ月に1回の治療を条件に軽度の病者を仮釈放したり、全国に7つの地域医療センターを設立してクリオン以外での治療も可能にしました。こうして隔離政策は緩和していきます。戦後、スルホン剤といった新薬も導入され、病者数は徐々に減少。1955年には隔離がとうとう廃止されました。


食料の配給にならぶ女性たち(写真:クリオン博物館)
当初は、アメリカが島民の生活を完全に面倒を見る、悪く言えばコントロールすることが計画されました。食料などの必需品と給付金を与え、週1回の治療や月2回の強制労働を義務づけるといったかたちです。アメリカ人の考える理想的な社会を作ろうと、質の高いインフラを整え、映画、雑誌、野球道具、楽器といった娯楽も与えました。でも、それと引き換えに、自分の生きたいように善く生きるという自由は、かなりの程度、奪われました。
彼らは週1回クリニックに通い、大風子油の治療を受けさせられました。アメリカのカーヴィル療養所では、病者の反発にあって実施できなかった。しかし植民地のクリオンなら、自由に実験できると考えたんです。大風子油の皮下注射は最先端の治療だったけれども、裏返せば人体実験で、皮膚や静脈の炎症、チアノーゼといった副作用を頻繁に起こしました。そのため半数以上の病者がクリニックでの診療を拒否した。そこでアメリカ人の行政官は、クリニックで医師のサインをもらわないと食料の配給をなくすといった対策をとったりもしました。それでも3割くらいの人が自分の体を実験台にされることを拒否し続けました。
食料の配給について調べていて驚いたのですが、当初、アメリカ人の行政官は牛肉やミルクを調達して、ハンセン病者に食べさせようとしていたんですね。「優れた人種」であるアメリカ人と同じ生活をさせれば健康になると信じたようです。

当時の医療器具(写真:クリオン博物館)
ただ、クリオンの病者は新鮮な魚をより好んで食べたようです。やがて彼らは自分たちで魚を捕ったり、野菜や果物を育てるようになりました。しかもそれで商売までするようになった。だんだんと島の人口が増えて、当局も配給する食料の確保に苦労するようになっていたので、彼らから食料を買いあげた。クリオンが作られた当初、人びとはアメリカ人の配給に頼っていたのですが、やがて自立的な経済基盤を築いていったのです。
しかも彼らの経済活動は、病者の地区と、医者や看護婦、シスター、快復者、子どもたちといった非病者の住む地区という島内の境界線を侵食していきます。2つの地区をつなぐ道路には鉄門があって、病者地区から戻るときにはそこで消毒をしないといけませんでした。病者地区だけで使用される硬貨も作られました。しかし、病者が自分でとった魚や野菜を非病者にも売るようになり、この硬貨が非病者の地区でも流通し出したのです。療養所の所長はけしからんといって取りしまろうしたけど、島民は小船で鉄門を迂回して取引をしたりして、うまく規制できませんでした。島内の隔離を切り崩していくような交易や生活が営まれていたんです。

結婚式を挙げたカップル(写真:クリオン博物館)

施設に収容された子どもたち(写真:クリオン博物館)
もうひとつ日本との大きな違いでいうと、断種もありませんでした。フィリピンはスペインの植民地だったので、カトリック教会が断種や堕胎を禁じていた。1930年代には日本の断種政策がクリオンの医師によって紹介されるのですが、教会の反対があって断念するんです。
ただ、子どもが生まれたら予算の負担は重たくなるし、子どもに病気がうつるかもしれないので、クリオンでは男女を分離して居住させようとしました。
彼らは家族、恋人、友人たちから強制的に引き離されてクリオンに連れて来られ、相当の孤独感に苦しんだはずです。そうしたなか、監視の目をかいくぐって、新たに恋人や家族を求める人たちの密会が繰り広げられます。その結果、非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子ども)の出産が相次いだので、当局は1928年に結婚を禁止して、厳格な男女分離を試みます。これに対して、男たちは結婚禁止令には法的根拠がないとして政府に請願運動をするんだけども、認められなかった。だったらということで、とうとう暴動がおきたんです。
棒きれや山刀を手にした数百人以上の男が女子寮を襲撃し、恋人たちを連れ出していった。2日間で、約600人の女性が寮を去りました。所長も警察も何も手をだせなかった。驚いたことに、多くの女性が喜んで男たちについていったそうです。当時を知る女性によると、女子寮の生活はシスターの厳格なしつけのもとにおかれて、「カゴの中の鳥」のようだったと語ります。彼女たちは、それが嫌で自由になりたく、事前に男たちと秘密のラブレターで連絡を取り合い、暴動に協力したようです。この事件は1932年のこと。同年に起きた日本軍の満州侵略にちなみ、この暴動は「マンチュリア」と呼ばれました。
結局アメリカ側は医者を含め、今後も男女関係をコントロールするのは不可能だと考えて、結婚を認めました。クリオン島の住民は、いわば「非市民的」な暴動によって、市民的な権利を勝ち取ったんです。アメリカはいろいろな物資を与えてくれたけど、いつまでもその言いなりになるのはゴメンだ。もっと自由に生きたいんだと。

現在のクリオン島(写真:篠田麻友)

クリオン島の家族。ほとんどの住民がハンセン病にルーツがある
とはいえ、子どもの問題が解決したわけではありません。当局は、子どもへの感染の危惧から、彼らを島の外に養子に出すことを強制します。だけど養子に出すまでのあいだ、修道女や看護師が少ない人数で増え続ける子どもの面倒をみたので、ケアが行き届かず小児病で亡くなることが多かった。子どもの暮らす施設がギュウギュウ詰めになって、衛生状況が悪化したことも原因です。やむをえず5歳くらいまでは親元で育てることが許されましたが、感染率は3割を超えたようです。それでも一緒に暮らせるならと、子どもを手放さない家族も多かったといいます。
最近では、クリオン島で生まれて養子にだされた子どもが年寄りになって自分のルーツを探るべくクリオン島に訪問することが増えているそうです。
クリオンは1955年に隔離政策が終了し、1992年には通常の行政単位である町になりました。今では、十数名が病院でハンセン病の治療を受ける一方、2万人ほどの島民が暮らしています。かつて療養所のあった地域では、ほとんどの住民がハンセン病者の子孫で、聞いてみると自分の親や祖父母は「レプロソ」だったと語ります。
調査中、背中に大きな鷹の入れ墨が入っているサリという男と仲良くなりました。彼はかつてセブ島で覚醒剤の売人をしていて、夜な夜な徹夜で賭博をしていたらハンセン病を発症し、クリオン島に来て治療を受けた。こんな無法者のことも、クリオン島の人びとは家族のように迎えるんですね。サリがクリオンの友人たちとラム酒を飲んでいるとき、ひとりが「サリに指がないのは失敗ばかりのヤクザだったからなんだ。失敗するたびに1本、2本と切って、足の指までなくなってしまったのさ」とジョークを言いました。身体の変形を笑うのは、日本の感覚では許されないことだと思うのですが、驚いたことに、サリを含めてその場にいる人たちが、みんな笑って同じジョークを何度も繰り返すんです。
でも、それは彼らが隔離された病者の子孫であることをみんな知っているから。頭で考えた「正しさ」よりも、身体的な感覚でつながりあっている。病の悲哀を身体的に共有しているからこそ、こんな不謹慎に思われるジョークでも笑い合えるのだと思います。

早稲田大生時代、フィリピンのワークキャンプにおいて
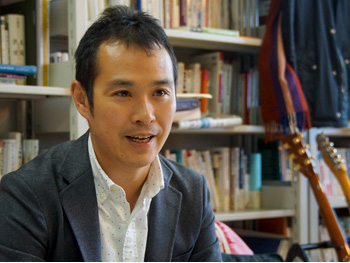
クリオンの歴史資料とインタビューから明らかにしたかったのは、大きく2つあります。
1つは他者への「愛」を批判的に検討するということです。クリオン島を統治したアメリカ人は、自分たちが理想と考える「市民的生活」をおくれるようにと、多くの予算をつかい、学校や図書館、郵便局、映画館といった施設を次々と建設し、また上質な衣料品やハンカチやネクタイも支給しました。
文明化のためには民主主義が不可欠だとも考えて、クリオン島の「大統領」と議員を選出するための選挙権を島民に与えました。20世紀初頭、アジアで初めて女性が参加した選挙といわれています。
アメリカは「愛」を語って物質的な福利を与える一方、フィリピン人の病者を「未開」から救い出し、「近代的な市民」へと発展させるべく規律化しようとしました。しかし、こうした統治はさまざまな制約や理不尽を強いました。結局のところ、アメリカの科学知と人種主義にもとづく「愛」は、ハンセン病者のより善き生を営もうとする欲望には合致しなかった。
科学的にデザインされた政策でも、人間が本来持っている欲望を押さえつけることはできない。当時のアメリカ人行政官は、フィリピンのハンセン病者は彼らのための善意や科学さえも理解せず、ちっとも言うことを聞かないと不平不満を行政文書に書き連ねています。
「善意」と「科学」でハンセン病者を救おうとしたアメリカの愛がいかに“いびつ”なものだったのかを明らかにすることで、ハンセン病者や他のマイノリティに対する自らの愛、そして権力を批判的に検討したかったんです。今日、たとえば様々なボランティア活動も、困難な状況におかれた他者への「愛」を語りながら、特定の価値を他者に求めたりしがちです。そんなとき、こうした視点は内省の契機を与えてくれるのではないでしょうか。

マニラのスラムに住み込みながら露天商で働いていた

植民地政府が禁止しきれなかった賭け闘鶏は今でもクリオンの娯楽

クリオンの子どもたち
理念的に他者と関わろうとすると、どうしてもエゴ的な「愛」に陥りがちですよね。自分たちの頭の中で他者のイメージを作り上げて、それと実際の他者が異なると、彼らを批判し出したりする。でも、他者との親密で身体的な交流を繰り返すことで、自分のエゴや思い込みが修正されていくこともあります。
私の場合、大学時代にフレンズ国際ワークキャンプ関東委員会(FIWC)という学生ボランティア団体に参加し、フィリピンのワークキャンプに参加するようになりました。中国でワークキャンプのNPO法人を立ち上げた原田僚太郎も同期です。(原田氏のインタビューはこちらから)
たとえばホテルに宿泊しながらのボランティアだと、他者は、「ハンセン病や貧困の村で暮らす人たち」という単なる集合体にとどまってしまいがちです。でもワークキャンプでは、現地の村で人びとと一緒に暮らし、ご飯を食べ、働くことで、個と個の関係を築いていかざるをえません。そのため、現地の人びとたちとの対話や、彼らからの異議申し立てを通じて、一人よがりなエゴを修正していくこともできますし、彼らの抱えている問題をより内在的に理解するきっかけも得やすいです。
もちろんワークキャンプに限らず、身体的な交流をする手段はいくらでもあります。私の場合、フィリピンで調査するときは、できるだけ住民のなかに入って一緒に生活するようにしています。そうやって彼らの生活感覚を理解しないと、どうしても上からの視点でしか理解できなくなってしまう。
もう一つ、クリオンの調査で明らかにしたかったのは、既存の秩序を疑うことの意味です。
今の日本社会では、誰かがつくったルールや道徳を、正しいのか間違っているのかもわからないまま「決まりだから」と盲目的に信じ込むことを求められているように感じます。私たちは、自分たちの欲望を押し殺して、思考停止の状態でシステムに従って生きることを強いられているのではないでしょうか。システムに逆らうような人間は、「輪をみだすな」と糾弾されてしまう。ハンセン病への差別や隔離政策が続いたのも、このような社会の枠組みの中にあったからです。
私の一番の関心は「秩序を誰がつくっているのか」という問題です。クリオン島の歴史で光を当てたかったのも、アメリカに豊富な物資を与えられ、飼い慣らされそうになりながらも、恋人との密会や暴動、強制労働や実験的治療の放棄といった実践によって、押しつけられた秩序を変えていったハンセン病者たちの姿でした。生の尊厳と自律性を取り戻すために、与えられた独善的なルールを無視した。その姿に、規律や道徳を強制するシステムへの抵抗の糸口があると思ったんです。

クリオンの夕日(写真:篠田麻友)
そうです。あえて挑発的に言えば、たとえば「ルールだから差別してはいけない」というのは、既存の秩序や道徳を盲目的に受け入れている点で、「ルールだから隔離すべき」というのと、あまり変わらないように思います。
むしろ、他者との相互的な関係性の中から生まれる葛藤や喜びといった感情、あるべき秩序に関する構想にもとづいて、既存のルールや道徳が本当に理にかなっているのか検討し、問題があればそれを改善していく。これは私が支持するアナキズムの考え方・実践でもあるんです。
そういう意味でクリオンの人々の実践は啓発的でした。自分たちで秩序を変えることができるということを忘れてしまいがちな日本人、特に若い人たちにはぜひともクリオンのことを知ってもらいたい。
フィリピンにはこういう事例がたくさんあります。何でも既存のルールに依存しがちな日本と違って、フィリピンでは人びとが自ら率先して秩序を変革しようしている。私はフィリピンを民主主義の先駆者だと考えているんです。だから、いつかは「アナーキー・イン・ザ・フィリピン」という本を書きたいですね(笑)。
取材・編集:寺平賢司 / 撮影:長津孝輔