ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination
People / ハンセン病に向き合う人びと

医薬品、食糧、すべてが欠乏し、希望を失っていた戦後の光明園。
暗いトンネルを抜けたあと、20代の望月さんが打ち込んだのは、
壁新聞と青年団機関誌の発行だった。
その活動の場はやがて光明園自治会、機関誌「楓」へと場所を移していく。
外島保養院から始まる療養所の歴史、19年に及んだ邑久長島大橋架橋運動。
当時の思い出について語っていただきました。
Profile
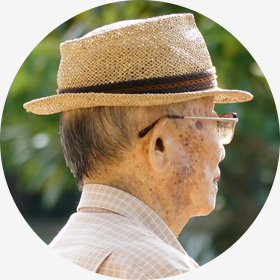
望月拓郎氏
(もちづき たくろう)
1926(昭和元)年生まれ。1946年、20歳のとき邑久光明園に入所。1948年より青年団で壁新聞、機関誌の編集に携わる。1952年、自治会選挙で副会長に初就任。以後、昭和30年代から20年以上にわたり自治会長を務めた。光明園の機関誌「楓」、自治会80年誌「風と海のなか」、100年史「隔離からの解放へ」等の編集にも参加する。

自治会の集まりや短歌、俳句の会合などに利用されていた恩賜会館。1941年の竣工当時は畳敷きだったが、高齢化、車椅子利用者の増加により現在は板張り、バリアフリー構造にリフォームされている
私が邑久光明園へ入園したのは1946(昭和21)年6月です。当時私は20歳でした。戦後すぐということもあって、園内の雰囲気は暗かったです。荒れた感じでもあった。最大の理由は食糧不足と医薬品の欠乏、このふたつだったと思います。
私が入園した年の6月から翌年の春までの間に入所者の25%が赤痢で亡くなっているんですよ。当時は病棟に配置される職員も、わずかしかいなかった。だから入所者が病棟で看護もするわけです。患者が重篤になった場合は、同じ部屋の者が隣のベッドに寝て特別看護をする。略して「特看(とっかん)」と言ってました。同部屋の者が看護に疲れてもうだめだということになったら、患者が所属する出身地の県人会、もしくは信仰している宗教団体の人たちが特別看護人を肩代わりするんです。先のことなんてまったくわからない。こういった状況では希望なんてもてません。
私が入った寮の近くに音楽の好きな青年がいて、入園して一週間くらい経ってから、よく話すようになりました。夕食が済んで消灯してから、ふたりで園内をぶらぶらとよく歩きました。ああでもない、こうでもないと、いろいろなことを話しながらね。私も彼も社会復帰の望みはありませんでしたから、おたがいに「3年生きられたらええか」なんてことをよく話しましたよ。「3年生きられたら、そのときにまた次の3年のことを考よう」と。3年刻みの人生です。
まもなくプロミンが導入されて、症状がだんだんよくなりました。食糧事情もよくなって、そうなると、生きる意欲というものをもつことができるようになってくるわけです。園内のよどんでいた空気がすーっと晴れたような感じでね、決してまだ明るいとは言えないけれど、今までの暗い状態から明るさの方へ一歩踏み出したな、という実感がありました。1948年頃には、かなり園内の雰囲気は変わっていたと思います。

青年団に入ってまず手がけたのは野球チームの結成だった。園内のリーグ戦などもさかんにおこなわれたが、望月さん自身は壁新聞や機関誌の発行で忙しく、スポーツに興ずる余裕はなかったという
私は48年から青年団に入ったんですが、まず最初にやったのは野球チームをつくることでした。若鷹チームというニックネームでね。しばらくして壮年団や光明園職員もチームをつくり、3チームで園内リーグ戦をするようになりました。卓球、テニスをやっている人も多くいました。テニスに関しては健常者の頃からやっていたという人もいて、かなり達者な人もいた。そういう人がコーチになって初心者に指導をするんです。
青年団では、いろいろな活動をやりました。野球チームづくりの次にやったのが壁新聞の発行、それから青年団の機関誌発行です。壁新聞の方は原稿さえ集まれば週一回くらい出しますよ、と園内放送で宣伝しました。最初のうちは物珍しさもあってか、みんな原稿を書いてきたんですが、そのうちに投稿者が少なくなって、あまり読まれなくなりました。
投稿がないので、私がほとんど原稿を書いていたんですが、これじゃ長くは続かないなと思いましたね。壁新聞というのは、みんながいろいろな意見を書くというのが、やはり面白いわけでね。埋め草の記事を書くくらいならいいけど、全部私ともう一人の二人で書くというのも違うなと。結局2年くらいで終わりということにしました。
機関誌「青年」づくりについては、当時はガリ版ですから原紙を切るのも大変で、目も疲れました。そんなわけで私自身はスポーツやったりするような余裕はなかったですね。青年団の仕事にかかりきりです。自治会まで出かけていって「青年団の詰め所くらい用意してくれ」と、かけ合ったりもしました。詰め所が確保できてからは、「青年」を隔月発行とし、そこでガリ版切ったり、製本したりしていました。
青年団に入るのは義務ではなかったんですが、園内には中学を卒業した25歳以下の軽症者は青年団に入るものだ、という暗黙の了解のようなものがありました。それで26歳になると、次は消防団に入るわけです。
青年団は運動会とか盆踊りといった園内の催し物全般を引き受ける。婦人会が後援して青年団が主催するんです。相撲大会なんかもやりましたね。消防団は緊急に備えて日々訓練するわけですが、私は消防団には入らなかった。強制ではなかったしね。

25歳になると自治会の被選挙権ができます。私は青年団を退団すると同時に自治会評議会というのに引っ張られましてね。そこで1年仕事したあと、数えの27歳(満26歳。1952年)で自治会執行部に選挙で放り込まれたんです。青年団でやんちゃしとったから、目をつけられていたんでしょうね。「あんなに元気あるんだったら、何かさせとけ」と。それでいきなり自治会の執行委員をやらされたんです。
当時の自治会選挙というのは立候補制ではなかったですからね。園内で目立っているやんちゃくれが「お前、自治会に入って何かせい」と引っ張られるわけです。後に投票所をきちんとつくって、そこに各自が投票に行くという形にしましたが、その頃は投票所もなくて、各部屋へ選挙管理委員が投票用紙を配って歩くんですよ。
当時の寮は大部屋で一棟に15畳の部屋が4つありました。玄関は左右にひとつずつあって、トイレも洗面所も2部屋共同でした。そんなこともあって生活の場というのは左右ふた部屋ずつになんとなく分かれていたんですね。1、2号室と3、4号室がそれぞれひとつのかたまりみたいになっとった。
投票用紙が配られると1、2号室、3、4号室にいる人がそれぞれ集まって「おい、あいつに入れとこうや」という話になるんですよ。「適当に名前書いといてくれ」なんてことを言う人もいた。そういうのはとくに選挙に興味ない人です。それで部屋ごとに票がまとまるんですよ。これは外島時代からそうだったみたいです。全国6ヵ所の療養所に散らばっていた外島の生存者が帰ってきて、1938年に開いたのが邑久光明園ですからね。新発患者の収容は翌年の39年から始まりましたが、それでも外島時代の習慣というのは後々まで残っていたと思います。
その後、自治会副会長を2年やったあと、30歳で自治会長になりました。以来20年、ずっと会長職。20年間、ほとんど自治会の仕事にかかりっきりです。その間、昭和43年から1年は瀬戸内からの派遣という形で全患協本部(多磨全生園)にもおりました。当時の全患協の会長は小泉孝之さん。小泉さんは長く全患協の会長を務めた方ですが、非常勤で普段は駿河療養所に入所してました。それで行動や会議のときは東京に駆けつける。そういうことになってました。

1953年のらい予防法改正闘争では全患協本部に代表を送らず非難されたこともあった。写真は国家賠償訴訟全面勝訴の翌年(2002年4月)、光明園入所者有志によって建立された勝訴記念碑
らい予防法改正闘争(1953年)は、私が執行部に入った次の年でした。このとき東北新生園と邑久光明園だけが闘争本部に代表を送らなかった。それでお前たちが闘争の足を引っ張ったんだ、と随分あとまで言われました。園内にも「全国の療養所は足並みを揃えないといけない、ぜひ代表を送るべきだ」という声はありましたし、私もそう思っていたんだけれども、賛否を投票で問うたところ、わずかな差で反対票が上まわったんです。それで光明園は中央行動には参加せず、作業ストなどもおこなわなかった。
ところが予防法改正闘争が終わったあと、栗生楽泉園で開かれた支部長会議には邑久光明園から代表を3名ちゃんと派遣しているんです。どうして予防法改正闘争のときだけ光明園執行部がああいった行動に出たのか、今もってよくわからないところがあります。これは執行部内部にいてもわからなかったです。
当時、私は2年間自治会の仕事をやったら、1年休みをもらってました。それで1年したら、また自治会の仕事に戻る。この繰り返しです。「楓(※邑久光明園の機関誌)」の編集をやったり、本つくったりというのは、この1年間の休みの間にやっていました。
「楓」は1936(昭和11)年創刊です。39年の室戸台風で外島保養園が壊滅し、生き残った人たちは全国の療養所へ委託療養という形で送られて離ればなれになってしまった。そんな療友たちの近況をまとめて、みんなで共有しようというのが「楓」創刊のきっかけだったんですね。今でいうところの情報誌です。私が「楓」の編集に最初に関わったのは51年でした。
編集部では、私が辛口の批評ばっかりするものだから「お前もなにか長いものでも書け」と、よく言われました。私がなにか書いたら今度はそれを辛口で批評してやろうと思ってたんでしょう。ところがとうとう、まとまった作品というのは、書きませんでした。なにか書こうとすると、どうしても私小説的なものになってしまう。それがいやで書かなかったんです。


外島保養院の話は部屋でお茶を飲んでいるときなど、折にふれて耳にしました。外島の入所者たちが問わず語りに「外島時代はこうだった」と話してくれるんです。最初はそういったところから外島の知識を得ていきました。私と同じ部屋には外島で自治会役員をしていた人がいて、県清志(あがた・きよし)さんといいました。もちろんこれは園名(偽名)です。
完成したばかりの光明園は工事のがれきが散乱していて、足の踏み場もないくらいだったそうです。建物を建てる敷地だけはなんとか整地してあったけれど、他の部分は何も整備してなかった。歩くための道すらなかったそうです。それで各地の療養所から帰ってきた比較的元気な人たちが、まず道づくりをやりました。奉仕作業ですから賃金はなし。「自分たちが住むところなんだから、やろうや」ということでやったわけです。夏は早朝から始めて、昼間の暑い時はさけて、夕方少し涼しくなったらまた作業する。そんな日々の連続で、なんとか園内の道ができたそうです。
県さんは外島でも自治会役員をしていただけあって、いろんなことをこと細かに覚えていました。外島事件(※)のときの院内の様子とか、村田院長の送別会はどんなだったとか、話してくれるわけです。
(※1933年、保養院内の保守派と革新派が対立。革新派の中でも中心的な人たち20名を追放した事件。「共産主義の赤化癩患者を一般社会へ脱出させた」との新聞報道があり、警察の捜査へと発展。最終的に村田正太(まさたか)院長が辞任に追い込まれた)
県さんは外島事件で20名が追放されたときも立ち会ったそうです。村田院長は餞別を包んで一人ひとりに手渡していたよ、と言っていました。
外島事件は新聞で騒がれ、警察の手入れなどもあって院長も苦境に立たされました。院長が厳しくしないから、こういうことになるんだと随分非難されたそうですが、村田院長は頑として大阪府の言うことを聞かなかったそうです。そういう気骨のある人でした。とにかく言い出したらきかんのや、とみんな口を揃えて言うくらいですから、筋金入りです。とにかく曲がったことがきらい。その代わり、言うことはみんな筋が通っているんですね。

そんなにすごい人だったんか、と訊くと「村田院長は患者だけでなく職員に対しても非常に厳しかった。それがまたよかった」と言うんです。とくに服装については厳しかったそうです。これは外島で職員をしていた人から聞いたんですが、制服(※外島の当時の制服は詰め襟)のボタンがひとつでも外れていると「そんなことでは駄目だ」と即座に叱られたと言っていました。まず紳士であれ、という人だったようです。村田院長というのは、外島の全入所者の強い信頼を得ていたと言えますね。
外島保養院で村田院長が断行したふたつの改革というのがあって、まずひとつが給食の改善。患者にとっては食事がとても大事なんだから、これをちゃんとしないといかん、ということで大阪府にかけ合った。そうして現在のような中央炊事場をきちんと整備し、食事の内容がみるみるうちによくなったそうです。もうひとつは教育。昭和初期の院内には文盲の人もいましたので、そういった人たちがせめて自分で家族に手紙が書けるように、返事を読めるように、と読み書きを教える場をつくった。
小学校もつくりました。小学校卒業後も学びたいという者には、院内の医者や事務官が先生になって中学過程(※旧制中学。12歳からの5年制)を教えたそうです。そのほかに課外授業としてエスペラント語(※19世紀末につくり出された世界共通語)を教えました。村田院長がエスペランティストだったんですね。
光明園が開園してかなり経ってからのことですが、大阪の吹田にNさんというエスペランティストの先生がいて、私はこの方とどういうわけか知遇があったんです。それで自治会でエスペラント講座をやってもらえませんか、とお願いしたことがありました。参加者を募集したら、かなり集まりましてね。「せめてエスペラント語で、はがきくらい出せるようになろうや」と、みんなで勉強しましたが、これも外島の影響かもしれません。実際、外島時代から勉強していたエスペランティストの人は、皆さんかなり達者でした。この講座は、けっこう長いこと続きました。

機関誌「楓」の連載記事を一冊にまとめた『旧外島保養院誌』。連載時に何部か余分に印刷しておき、それをハードカバーに製本しなおすという手法で作られた。外島時代の様子を伝える貴重な資料
活字や本という形で外島保養院の歴史、邑久光明園の歴史を残したいという思いは、若い頃からもってました。「楓」の編集をやっているときも、ハンセン病発病のために迫害を受けた家族の手記を載せようとか、いろいろな企画を考えましたね。当時、台湾で教員をしていたときに発病して引き上げてきた人が光明園にいて、その人にも手記を寄稿してもらいました。
『旧外島保養院誌』(桜井方策著 1974年刊)という本の発行も手伝いましたが、これは「楓」に連載したものを合本としてまとめたものです。「楓」を印刷するときに、何部か別刷りを余分に刷っておいて、そうやって毎号取っておいたものを、一冊の本として製本したんですよ。だから邑久光明園の外には、ほとんど存在していないと思います。今から考えると本にしておいてよかった。まとめておかなかったら、今頃この外島関連の資料も散逸していたかもしれませんからね。
桜井方策さんという人は外島保養院で医者をしていた人で、初代の医長です。この人の文章がまたおもしろいんですよ。講談調で、話がけっこうあちこち寄り道するんだね。全然関係ないエピソードがしばらく続いて、閑話休題でようやく元に戻ってくる。そこが味でもあった。桜井さんは、たしか外島のあと松丘保養院の園長も務めたんじゃなかったかな。
桜井先生は当時の守屋(睦夫)園長に紹介していただきました。後世に残るような外島の記録がないというのも困ったことだと思って、誰かいい人はいないですかと守屋園長に相談したんですね。そうしたら「外島にいた桜井先生がいいんじゃないか。あの人は文人だし、書いてくれるかどうか、私から訊いてみよう」と言ってくださった。それで「楓」での連載が決まったんです。
守屋園長は自治会の活動にもたいへん理解がありました。岡山医大(旧制)を出て、すぐ大島青松園に勤めたという方で、外島保養院が災害にあったときも救援隊の隊長格で大阪に来ているんです。機帆船(※動力付きの帆船)に乗ってね。当時はまだ青年医師です。桜井先生とも、そのころに知遇があったんでしょう。

「瀬溝」の上に架かる邑久長島大橋。かつては手漕ぎ船で行き来する以外に交通手段がなかった。架橋運動開始から19年を要した橋は、2018年に架橋30周年を迎える
邑久長島大橋の架橋運動にも初期から関わりました。最初は夜勤の職員の人たちが海が荒れたら通勤できなくて困るから、瀬溝に歩道橋でも架けようや、という話がきっかけだったんです。当時は手漕ぎの渡し船しかありませんでしたからね。試算してみたら、光明園の年間整備関係予算で歩道橋だったらなんとかなりそうだということだったので、それなら、という話になったんです。
その後、「せっかく橋をつくるんだったら車も通れる橋にして利便性を高めようじゃないか」ということになって、その方向で話がまとまりました。そこから長島愛生園自治会と合同で架橋促進運動が始まっていったんです。最終的に橋がかかるまでには19年という長い年月がかかりました。
橋を架けるときに難しいのは、橋の予算がつけばそれで終わりじゃないというところなんですね。邑久長島大橋の場合は、取り付け道路を完成させて裳掛小学校前の県道までつながないといけなかった。間はすべて民有地でした。土地の権利者は90人以上いたそうですが、これをすべて旧邑久町の職員が説得にまわってくれたんです。これはちょっと難儀そうやな、というところは町議会の議長がまわってくれたりしてね。
当時の邑久町長が頑張ってくれたおかげで、なんとか取り付け道路の地主全員の了解を取り付けることができた。説得に説得を重ねて、開通の日を迎えることができました。祝賀会では、その町長さんも挨拶されたんですが、感極まってしまって、ほとんどことばが出なかったですよ。あの町長は、今思い出してみてもすごい人でしたねえ。
橋が架かったときはみんなで朝から現場に行きました。一日中ずっと見守っていて、架かった瞬間は全員で万歳三唱だ(笑)。それで、開通式の時、邑久高校ブラスバンドを先頭に渡りぞめをした。あの感動と高揚感は忘れられない思い出のひとつです。まさに「人間回復の橋」だと言えますね。
取材・編集:三浦博史 / 写真:長津孝輔