ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination


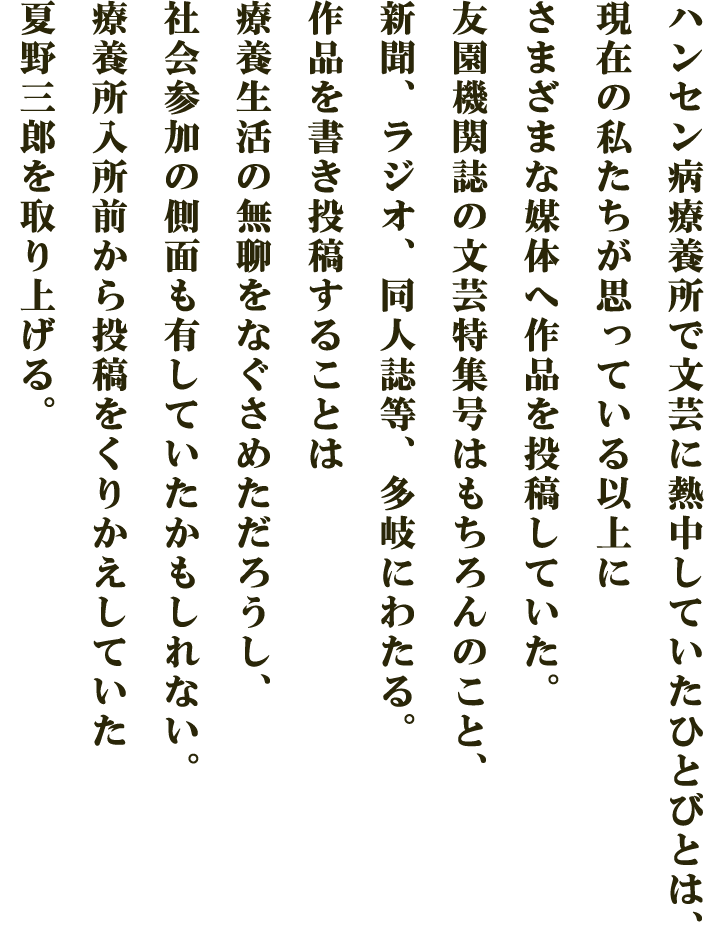

娯楽の少なかった時代、ハンセン病療養所では園内劇団による芝居や映画の上映などと並んで、夏祭りや盆踊り大会は大きな娯楽だった。国立療養所の中ではもっとも後発の駿河療養所(1945年6月に開所)も例外ではない。今年(2017年)8月3日、駿河療養所で開催された「駿河納涼盆踊り大会」で「駿河音頭」が53年ぶりに復活を遂げた。駿河に集まるフィールドワークのメンバーの一人・石崎恵子さんが、入所者の思い出話の中に頻出する駿河音頭に関心を持ち、作曲した小田猛さんに歌ってもらい採譜を行い、アップテンポの曲に仕上げたものだ。(1)
1951年、自治会文化部は顕彰をつけて駿河音頭と駿河小唄の公募を行った。(2)当時、夏祭りは3日間にわたって開催され、初日は福引大会と盆踊り、二日目はのど自慢大会、三日目は仮装大会で構成され、入所者たちは思い思いの仮装をして、中でも若くて元気な人たちは夜明けまで踊っていた。駿河音頭、江州音頭、八木節などが主流だったが、こうした盆踊りの活況を重視した自治会文化部が、新しい駿河音頭を募集することにしたのだった。
駿河療養所においても俳句や短歌に励んでいたひとびとがいて、彼らは競って作詞をはじめた。夏野三郎もその一人だった。駿河神社のある道を進み山道を抜けると芦ノ湖へ出る。春の遠足は入所者の楽しみのひとつだった。先に記したように夏は盆踊りが盛んで、こうした季節ごとのできごとを織り込み、5番まで作詞して駿河小唄とともに自治会文化部へ提出したという。結果、夏野作詞の両作品が一等を勝ち取り百円の賞金を得たという。入所者により曲も振り付けも考案され、園内の芙蓉楽団が演奏をするスタイルができ、夏祭りに欠かせないものとなっていった。
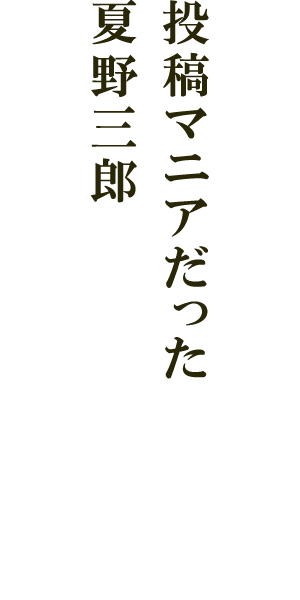
それにしても駿河音頭、駿河小唄の双方ともに一等を取った夏野三郎とはいったいどんな人物だったのだろうか。じつは夏野は駿河療養所入所前から雑誌への投稿で賞金を稼いでいた経験を持っていた。夏野は1922年に愛知県名古屋市内で生まれ育った。1944年にハンセン病の初期症状が出て兵役免除となった。軽症だったため除隊後は軍管理工場で働いていたという。名古屋の大空襲にも遭遇するが生き延びて、戦後は農機具工場に勤務していた。しかし戦時中の無理がたたったのか病状が進行し、自宅療養の生活に入った。少年時代から『少年倶楽部』などに投稿を重ね賞金をもらっていた夏野は、療養生活の無聊を慰めるため新聞や雑誌の標語、文芸、脚本募集などに熱中するようになる。
朝日新聞をはじめ、毎日、読売、中日の新聞を購読することにした。毎朝バサッとほうり込まれる新聞をひろげて、懸賞募集の記事を探すのである。かならず、どこかの官庁、市町村、あるいは団体などで、原稿募集などの記事が掲載される。それをハサミで切り抜き、スクラップして、原稿の締切り日に合わせて予定表を作るのである。机の上には、原稿用紙、辞書、参考書など、雑然と積み上げた前で書くことになる。多くの作品が集まるので、なかなか、金的を射止めるのは、簡単ではない。葉書で間に合う短歌・俳句・川柳、それに標語などになると、一つの募集に二十も三十も作句して、集中的に投函するのである。
(夏野三郎「お墨付」『紫陽花』97~98ページ)
夏野は当選発表を心待ちにし、当選通知状を「お墨付」と称してノートに記録していった。懸賞で求められているものを読み取り、その要望に合わせた作品をいくつも書いた。入選すると新聞などに名前と住所が掲載されることもあり、見知らぬひとから感想などを記した手紙が届くようになり、さまざまな地域にペンフレンド仲間ができたそうだ。ラジオドラマの募集も盛んで夏野は脚本も執筆するようになった。「労働省とNHKの共催による工場災害防止ドラマ」の募集があり、夏野は脚本を送った。1950年のことで、ちょうど夏野が駿河療養所に入所した日に、母親のもとへお墨付と賞金が届いたという。療養所へ入ってからも外部への投稿もつづけていたというから、筋金入りのものであった。
東亜通信社が公募した『豊年てんぷら油』の広告ドラマ、NHK山形放送局と盛岡放送局の開局三十周年記念事業で公募した放送劇・児童劇にも佳作入選したという。残念ながらその後、虹彩炎や熱こぶに悩まされたこと、また「療養生活の惰性に流さ」れ、原稿執筆から遠ざかっていった。いずれにせよ、こうした地道な投稿の継続が、駿河音頭の入選の下敷きになっていたのである。

夏野の著作『紫陽花』の序文は、親しく交流していた多磨全生園の光岡良二が執筆している。光岡によれば夏野は所内の購買部主任や入所者自治会の執行委員、評議員などもつとめていたという。当然、駿河療養所の入所者自治会会長を数度つとめた小泉孝之とも親交があった。小泉は1965年から83年の長きにわたって全患協(全国ハンセン氏病患者協議会、現・全療協)会長をつとめた人物で、戦前、栗生楽泉園、多磨全生園に在園していた頃から小説を執筆していた。
ちょうど夏野が入所した1950年は、小泉、都波修、上村真治ら10名近くで小説を読んで勉強する輪読会を結成した時期であった。1955年に詩人・中原中也の弟で詩や創作も手がけていた中原呉郎が、医師として駿河療養所に赴任する。中原の赴任をひとつのきっかけとして、輪読会は発展的に解消し駿河創作会が結成される。結成から1970年代後半までが、駿河における創作活動が活発だった時期である。
しかし駿河療養所は機関誌『芙蓉』を1949年から発行していたが、予算不足もあり幾度かの中断を経て1960年には廃刊に至った。主要な作品発表媒体である『芙蓉』の廃刊は、創作会のメンバーにとって大きな痛手であった。もちろんほかの療養所機関誌の文芸特集号等への投稿は行っていたものの、彼らは自身の手による同人誌の発刊を望むようになった。1964年に入所者の小泉、都波修、上村真治、牧夾太郎、それに医師の中原呉郎を加えた5名によって、文芸同人誌『山椒』が発刊される。『山椒』はガリ版で、発行人は小泉孝之、編集人は都波修、発行所は駿河創作会山椒同人と創刊号の奥付にある。印刷は駿河会印刷部が担当しており、入所者の伊藤秋夫、向井之男が原紙を切っていた。
同人誌の難しさは、作品もさることながら、それ以上に経済的困難がある。年二、三回発行の企画をしているが、乏しい療養所生活の中で継続するのは並大抵のことではない。が、発芽した山椒は、大木になるまで、どんな苦難を克服しても育てねばならぬ。『癩文学』とか『療養所文学』と、文学に迄あつた偏見を除去するためにも……」
(都波修「編集後記」『山椒』創刊号、1964年2月)
引用した都波の文章にあるように、経済的な問題もあり『山椒』の発行はスムーズに進んだわけではなかった。当初は年4回発行していたが、年に2~3回と徐々にペースは落ちていった。1975年6月、中心メンバーだった中原呉郎が亡くなり、同年11月に発行された第32号は「中原呉郎遺稿集」として特集を組み、中原の死を悼んだ。それに加えて1976年の暮れに創刊以来の同人である上村真治も亡くなった。この二人を失ったことが大きかったのだろうか、第35号(1977年9月)で「故上村真治追悼号」を組み、それを最後に『山椒』は発行を止めた。
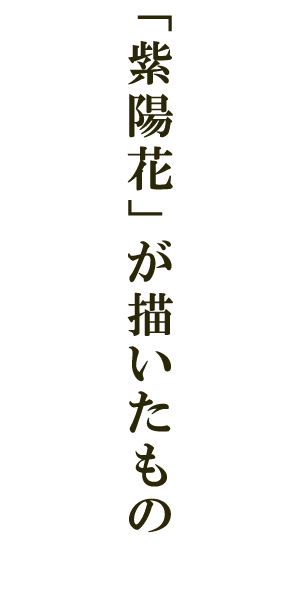
しかしながら自分たちの文芸誌を持った『山椒』同人たちの文芸熱にあてられたのだろうか、夏野三郎もふたたび筆を執るようになったようである。1966年12月発行の『山椒』第10号に、夏野は短編小説「余燼」を発表。つづけて第11号(1967年2月)に「商骨」、第12号(1967年6月)に「金色」、第13号(1967年9月)に「代償」、第14号(1967年12月)に「紫陽花」と連続して短編小説を発表している。このうち「紫陽花」は「銀扇」というタイトルで1967年12月九州三園共同全国文芸特集号に佳作入選、「金色」は1968年の『多磨』文芸特集号で佳作入選を果たしている。
その後、夏野による小説は発表されていない。随筆はいくつも書かれていて、『紫陽花』、『目と手を借りての旅』(私家版、1989年)にまとめられている。数少ない小説はどのようなものだったかというと、ハンセン病を題材としたものは「紫陽花」一編のみである。たとえば「代償」はノモンハン事件を題材とした作品だ。ロシア語と英語に堪能な汽船会社の社員である主人公が、満州国に亡命してきたソ連の大将の通訳を憲兵司令部からの要請によりつとめることになり、交流を深めていく中でノモンハン事件が起きる。「金色」は陶器職人である主人公が母娘の心中未遂を発見し、彼らの面倒を見るようになる話だ。
おそらく夏野自身の戦時中の経験をもとに発想して書かれたと思われるのが「紫陽花」(4)である。主人公の早瀬孝一は名古屋市にある軍需工場で働いていた。工場長の曽根は友人だったが召集され、早瀬は請われて曽根の妻・律子と嬰児である博が住む家に、勤労学徒数名とともに寄宿することになる。やがて日本舞踊をたしなむ律子にあこがれを抱くようになるが、戦況はますます悪化し、名古屋市も空襲に見舞われるようになった。律子と博をかばって大怪我を負った早瀬は、踊りに使う大事な銀扇を律子に請い譲り受ける。治療が進んだにもかかわらず一か所癒えない傷があり、早瀬がハンセン病を発病していることが発覚する。早瀬は律子と二度と会わないことを心に決め放浪の旅に出て、療養所に入所した。失明におびえながら過ごす中、律子が面会に訪れる。
早瀬にとって入所前のもっとも大事な思い出は、律子から譲り受けた銀扇に象徴されている。面会を断った早瀬に律子は手紙を残す。しかし早瀬の視力は弱まるばかりだ。「手や足がたとえ腐蝕されていってもいい。絶望的な盲目になることだけは嫌だった。早瀬は律子の手紙だけは代読してもらいたくなかった」
ハンセン病を病むという経験において、失明という事態はひときわきびしいものだった。失明が迫る絶望感と、それでも何十年経とうとも思いを寄せる女性からの手紙を自らの目で読もうと誓うラストシーンは哀切でありながら、暗黒に占められてはいない。

(1)「踊り継いで」駿河音頭 復活」『東京新聞』朝刊静岡版、2017年8月1日
(2)以下、駿河音頭と夏祭りについては、とくに断らない限り夏野三郎「駿河音頭夜話」(夏野三郎『紫陽花』現代書房新社、1981年)による。
(3)前掲夏野「お墨付」を参照。
(4)夏野三郎「紫陽花」(前掲夏野『紫陽花』)。

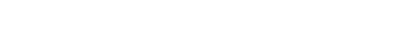
大学1年生のときに佐藤真監督のドキュメンタリー映画『阿賀に生きる』を観て水俣病問題と関わるようになり、病と社会の関係に興味をもつ。大学院で群馬県の草津温泉にあったハンセン病者の集落「湯之沢部落」の研究に取り組む。大学院修了後、皓星社に入社し、ハンセン病に関する書籍を数点担当。現在、フリーで出版の営業や編集をするかたわら、東京と静岡を拠点に「ハンセン病文学読書会」を主宰している。共編著に『ハンセン病文学読書会のすすめ』(2015、非売品)、共著に『ハンセン病 日本と世界』(工作舎、2016)がある。『ハンセン病文学読書会のすすめ』『ハンセン病を学ぶためのブックガイド』(工作舎、2016、非売品)をご希望の方は下記のメールアドレスにご連絡ください。
sbenzo.jokyouju■gmail.com(連絡先:佐藤健太)※■を@に変換してください
2017.6.22
2017.11.28
2017.11.28
2017.11.28