ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination


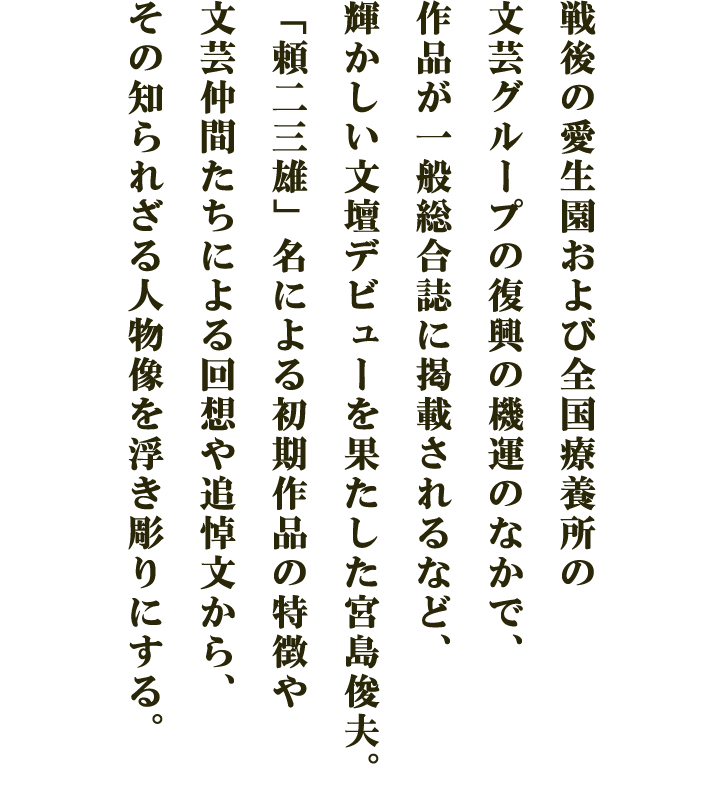
機関誌『愛生』の休刊から1年余りして日本は敗戦を迎えた。それから間もなく長島愛生園で文芸グループ復興の動きは起こった。1946年10月、甲斐八郎、宮島俊夫らが中心となって、長島創作会は復活を遂げている。名称はあらたに長島文学会とされた。(1) ほかの園でも続々と創作グループが活動を再開、もしくは新たに結成されていった。1947年6月文章会再開(菊池恵楓園。文章会は1934年設立)、1948年多磨創作会結成(多磨全生園)、1950年4月栗生創作会結成(栗生楽泉園)、1951年頃に駿河創作会結成(駿河療養所)等である。創作分野において、とりわけ長島愛生園は動きが早かったと言えよう。
主要な作品発表媒体の機関誌『愛生』も1947年2月に復刊し(表紙には創刊号とあり、巻数も第1巻第1号と数え直されている)、全国の療養所入所者を対象とした文芸特集号も1950年11月号から再開されるようになる。ハンセン病療養所における創作活動は息を吹き返しこれまでにない活況を呈するが、各園の書き手たちをいっそう創作活動に駆りたてる出来事が1949年に起きた。宮島俊夫の短編小説「癩夫婦」が、商業誌の『新潮』に掲載されたのである。
宮島俊夫の略歴を『ハンセン病文学全集』の「著者紹介」と『愛生』掲載の略歴をもとに簡潔にまとめるとつぎのようになる。宮島は1917年愛知県生まれ。県立中学校を中退し1939年5月愛生園に入園する。園内の文章会、創作会のメンバーであり、入園翌年から創作活動を開始。1949年『新潮』に「癩夫婦」「レプラ・コンプレックス」を発表。そのほか合同作品集『深海の魚族』(1951年)、『小島に生きる』『廃園の灯』(1952年)に作品が掲載されている。1955年2月15日に38歳で亡くなった。没後に『癩夫婦』(保険同人社、1955年)が刊行されている。(2)
これだけでは宮島の人物像は見えてこない。そこで長島創作会メンバーによる宮島の追悼文などから、より詳細に宮島の経歴を追っていこう。つぎに見るのは甲斐八郎の追悼文だ。
ぼくと宮島君との交及(ママ)がはじまつたのは、昭和十四年からだつた。彼が入園してまもなくだつたようである。ぼくは、それ以前すでにこの療養所に二年ばかりすごしてきていたが、その頃いた立田寮だつたか大山寮だつたかの青年の寮というのへたずねてくれたのである。そのころから文学の「ブ」もわからぬまま幼い文章を「愛生」誌に発表したりしていたぼくを、彼はよんでいてくれて、「ほう、ここに本当の文学をやるものがいるぞ」と、これは彼との初対面後の彼の率直な表現だつたが、そんな言葉で、ぼくたちの交流ははじまつたのだつた。
(中略)彼は、そのころから、すでに中学時代から同人雑誌などもやつたことがあるという経歴の持主で文学についての一家言は、すでにもつていたようだつた。
(甲斐八郎「宮島君との交友」『愛生』第9巻第5号、1955年5月)
甲斐の回想によれば、宮島は愛知県の県立中学校にいた頃から文学仲間と同人雑誌をつくっていたようである。誌名などの詳細はわからないが、早熟な文学青年であったことがうかがえる。創作を発表していた甲斐八郎を入園早々に訪ねて交友を結ぶようになったのもうなずけよう。宮島は『愛生』に作品を寄せていた書き手の中から「これぞ」と彼が思う人物を訪ね回っていたのだ。吉成稔も宮島を「昭和十四年からの友」(3)と記しているように、園内で真剣に文学に取り組む仲間を発見しては交友を結び、文学論をたたかわせていたのだろう。文学青年・宮島の社交性に富んだ性格は、長島創作会結成の空気を醸成するのに一役買っていたにちがいない。
愛生園の友人たちによる回想からうかびあがる宮島像は、きわめて明朗なものである。「どう見ても軍人には不向きなタイプだった」とは園内売店でともに働いた佐治早人の弁だ。とても美しい声の持主で流行歌を歌うのを得意としており、舎から聞こえる宮島の歌声はすぐさま園内中の話題となり、当時の流行歌手・東海林太郎をもじった「愛生太郎」というあだ名すらできたという。
氏の入園した年の秋ごろだつたか、隠芸大会があつて、勿論氏もひき出された。氏は、ステージに立つて、愛嬌をふりまきながら、得意の喉をふるつた。観衆は、東海林太郎、愛生太郎と、声援を送り、「支那の夜」でアンコールがおわつたものの観衆は、更にアンコールを要求して、氏をステージから容易におろさなかつた。
(佐治早人「故宮島俊夫氏を偲ぶ」『愛生』第9巻第5号、1955年5月)
こうした明朗な性格とふるまいによってまるで流行歌手のような人気を園内で博す一方、宮島は創作にも積極的に取り組み、入園翌年には頼二三雄のペンネームで「或る忌避」という短編小説を『愛生』第10巻第5号(1940年5月)に発表している。療養所文芸における宮島の記念すべき初作品は4ページの短いものだった。
工場で働いている主人公・野中のもとに故郷の叔父から急ぎの電報が届く。召集令状が来たのですぐに帰れという内容だった。列車を降り夜も明けきらぬ中を野中はK村へ向かって歩いた。しばらく待てばバスが出るが、明るくなって知った人と会うのは避けたい。じつは一週間前から野中は自分が「癩病」であると確信していたのだ。故郷を出て「こつそり旅で死んだ」父と同じ病であると……。そして自分も「子として父の示した道を踏」もうと心に決めていた。しかし叔父に反対され「聯隊医務室から直ぐさま陸軍病院へ運ばれ、三週間程してこゝへ転送されてきた」。自分は召集令状が来た時に死ぬべきだったのか、生きていなければいけなかったのかという問いかけで終わる。
本作は最後の節で、主人公が「こゝ」へ来た経緯を誰かに話していることが明らかになる構成をとっている。「こゝ」はハンセン病療養所と読んで差し支えないだろう。随筆や評論の書き手だった佐治早人の追悼文には、宮島が傷痍軍人だったとあり(4)、代表作となった「癩夫婦」でも主人公の「私」が傷痍軍人だったことと照らし合わせると、「或る忌避」は宮島の個人的体験をもとに書かれたものではないかと推測できる。どこまでが宮島の来歴と重なり合うのかわからないが、私小説の体裁を取ることが多かった戦前の療養所文芸の特徴を、宮島の処女作も持ち合わせていたとみてよいのではないだろうか。
その後、同じく頼二三雄名義で「秋夜」(1941年11月)を、峰島俊吉名義で「流れあえず」(1942年2月)を書き、1943年1月に発表した「口碑」から宮島俊夫名義を用いるようになった。
さて、宮島は療養所機関誌のみならず外部の文芸雑誌、同人雑誌などにも積極的に投稿をくりかえしていた。長島創作会の阿部肇がまとめた簡易な年譜と創作会略史(5)によれば、「癩夫婦」が掲載された『新潮』以外にも1946年『文化タイムス』に「いも」、1948年広島の同人雑誌『広島文学』に「夜の記録」、1951年京都の『ブジストマガジン』に「或る看護婦の手記」を連載、1952年同人雑誌『作家』に「隔離病室」「泥濘」を発表したとある(6)。
同人雑誌は本来のところ、同じ目標を志して参集したひとびと(同人)が、作品を発表するために互いにお金を出資しあって発行されるものだ。では宮島は『広島文学』『作家』の同人だったのだろうか。『広島文学』については不明だが、『作家』に宮島が投稿できた理由は推測できる。
『作家』は戦後初の芥川賞受賞作家だった小谷剛が主宰していた同人雑誌である。1948年1月に創刊され、小谷没後の現在も『季刊作家』と改題し発行をつづけている。第2号を刊行するものの同人間の意見対立により解散。小谷、伊藤■=サンズイ+亢(中部日本新聞出版部長)、亀山巌(同企画局)ら5名が残り『作家』の発行をつづけていく。同人制度を敷いていたが同人費を徴収することはなく、産婦人科医を本業とした小谷が一切の費用を負担するという特異なものだった(7)。『作家』が同人制度を確立するのは1959年6月のことであり、それまでは雑誌購読料さえ払えば会員となり、会員には作品を投稿する資格が与えられていた。原稿が採用されると同人となるが同人費は不要で、作品を掲載するための掲載料を払う必要もなかったのだ(8)。
創刊号から書店へ配本されていた『作家』は、全国に数多存在した同人雑誌のなかでも著名であり、療養所生活で自由にできるお金の少ない入所者にとって作品掲載のハードルが低い媒体であったといえよう。宮島のほかにも入所者が作品を送っていた可能性はある。また新人作家の育成に熱心だった小谷の編集姿勢は、文学に取り組む療養所の無名作家たちを引き寄せるに十分だった。のちに小谷は1955年から57年の間、『愛生』文芸特集号で創作部門の選者をつとめている。宮島の投稿作品に親しんでいたことも、選者を引き受ける動機となったのではないだろうか。
1941年に菊池恵楓園から長島愛生園へ転園してきた森田竹次(9)も長島創作会のメンバーだった。共産党長島支部の初代支部長となり全患協運動で活躍、『全患協斗争史』や評論集『偏見への挑戦』などを遺した森田だが、恵楓園時代から文章会に参加し創作にも取り組んでいた。その森田の短編小説「幽明の記」が婦人雑誌『藝苑』(10)に掲載されたのは1947年7月のことだった。厳松堂書店を発行所とするこの雑誌は1944年8月に創刊。「戦時における「翼賛文学」の一翼を担っていた」が、戦後、編集人となった堀江義衛の大きな方針転換により「新女性誌」として復刊を遂げた(1945年9月)。「新日本文化の再建設」をうたい「文藝における創作指導や新人作家の発掘・育成を重視」するという特徴を持った新生『藝苑』は「在野にあって文学研究を志す青年女性にとって必須の雑誌」であり、1947年度には3万部の発行部数に達していた。
この森田の快挙に大いに刺激された宮島は作品を書き『新潮』編集部へ送った。「癩夫婦」は見事に『新潮』第46巻第2号(1949年2月)に掲載され、療養所の無名作家たちを驚かせた。しかし宮島はその後「レプラ・コンプレックス」をふたたび『新潮』に発表したもののスランプに陥ってしまった。宮島の親友・吉成稔はこう証言している。
『癩夫婦』『レプラ・コンプレツクス』と中央文壇にデビユーした宮島さんが、その後マンネリズムというか、やはりブランクの時期が出来てね。しよつ中、僕にも一種の焦燥感をもつて書けないと云つていた。
(長島創作会座談会「宮島俊夫氏を偲ぶ」『愛生』1955年4月)
作品は発表していたものの、宮島自身は納得のいくものではなかったようだ。そんな折「癩予防法」改正問題が起き、宮島はその運動に飛び込んでいったという。だが政治に積極的にかかわりながらも宮島は文学への思いを捨て去ったわけではなかった。ふたたび吉成の言葉を引けば「予防法改正当時に生じたあらゆる現象を、いろいろのタイプの人間を駆使して歴史的な流れの上に立つた力作を書きたいと死の寸前迄口癖のように云つていたんだ」(11)。だが残念なことに作品を書く前に宮島は亡くなってしまったのである。らい予防法闘争をもとに宮島がどのような構想を立て、どんな作品に結実しただろうかと思いを馳せずにはいられない。

(1)1952年には長島創作会に再度変更されている。
(2) 『ハンセン病文学全集』第4巻 記録・随筆、皓星社、2003年、776ページおよび阿部[肇]「宮島俊夫氏の略歴及その作品活動」『愛生』第9巻第5号、1955年5月を参照した。『ハンセン病文学全集』編集部は各療養所入園者自治会等の協力の下、できるかぎり著者の略歴やペンネームを収集し記載する方針を取った。
(3)吉成稔『見える 癩盲者の告白』キリスト新聞社、1963年、40ページ。
(4)佐治早人「故宮島俊夫氏を偲ぶ」『愛生』第9巻第5号、1955年5月。
(5)阿部[肇]「宮島俊夫氏の略歴及その作品活動」『愛生』第9巻第5号、1955年5月、および無署名「長島創作会十年略史」『愛生』第5巻第1号、1951年1月。
(6)『文化タイムス』『ブジストマガジン』『広島文学』に掲載された諸作品については未確認である。「長島創作会十年略史」には「夜の記録」は『広島文学』に掲載されたとあるが、甲斐八郎によれば「広島の『郷友』という同人雑誌」(長島創作会による座談会「宮島俊夫氏を偲ぶ」『愛生』第9巻第5号、1955年5月)に掲載されたともある。どちらかが間違って記述しているか、『広島文学』がのちに『郷友』と誌名を変更した可能性があると思われる。
(7)戸田鎮子『作家小谷剛と『作家』』中日出版社、1999年、88~90ページ
(8)似たケースとして1950年に作家・丹羽文雄が創刊、主宰した同人雑誌『文學者』がある。森下節は「丹羽文雄個人の身ゼニによって出された雑誌として有名だった」と記している。森下節『新・同人雑誌入門』皓星社、1980年、21ページ。
(9)森田竹次「菊池恵楓園と私」『菊池野』第27巻第2号、1976年2月。
(10)以下、『藝苑』に関する記述および引用はすべて吉田健二編著『占領期女性雑誌事典――解題目次総索引 第2巻『家庭クラブ』~『越路』』金沢文圃閣、2004年の「解題」に依っている。
(11) 長島創作会座談会「宮島俊夫氏を偲ぶ」『愛生』1955年4月。
大学1年生のときに佐藤真監督のドキュメンタリー映画『阿賀に生きる』を観て水俣病問題と関わるようになり、病と社会の関係に興味をもつ。大学院で群馬県の草津温泉にあったハンセン病者の集落「湯之沢部落」の研究に取り組む。大学院修了後、皓星社に入社し、ハンセン病に関する書籍を数点担当。現在、フリーで出版の営業や編集をするかたわら、東京と静岡を拠点に「ハンセン病文学読書会」を主宰している。共編著に『ハンセン病文学読書会のすすめ』(2015、非売品)、共著に『ハンセン病 日本と世界』(工作舎、2016)がある。『ハンセン病文学読書会のすすめ』『ハンセン病を学ぶためのブックガイド』(工作舎、2016、非売品)をご希望の方は下記のメールアドレスにご連絡ください。
sbenzo.jokyouju■gmail.com(連絡先:佐藤健太)※■を@に変換してください
2017.6.22
2017.11.28
2017.11.28
2017.11.28