ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination
People / ハンセン病に向き合う人びと
観光客で賑わう群馬県の草津温泉街。
その東側に、かつて「湯之澤」と呼ばれるハンセン病者の集落があった。
世界のハンセン病コロニーに照らしても特異なのは、この集落が隣接する草津町と持ちつ持たれつの関係をつくりつつ
明治中期から国の隔離政策が始まる昭和初期までの約60年間にわたり自治を成立させていたことだ。
この実績は、国立療養所栗生楽泉園の「自由地区」として受け継がれた。
そして、当時の集落と町に大きな影響を与えたのが、イギリス人宣教師コンウォール・リーによる聖バルナバ・ミッションである。
草津を訪れ、湯之澤にまつわる歴史の痕跡をたどった。

湯畑の傍らにある「白旗の湯」は、源頼朝の伝説とともに、ハンセン病とのかかわりがひそむ草津の歴史的なシンボル。
草津温泉のシンボル「湯畑」。あたり一帯に独特の硫黄の香りが漂い、豊かに湧き出る澄んだ湯の底は白い湯の花で覆われている。すぐ脇には、白旗源泉がある。白旗は源氏の旗印だ。地元には、鷹狩で通りかかった源頼朝がこの温泉を発見したという言い伝えがある。湯之澤部落ができるまで、この源泉は頼朝が座り入浴したことにちなみ、「御座の湯」と呼ばれていた。
草津温泉は、古くからハンセン病に効くとされてきた。頼朝のもとに薬師如来の権化である童子が現れ、他のさまざまな病とともに「白癩(はくらい。ハンセン病のこと)」を挙げ、この湯によって病苦から救われると告げたという。もっともこの話は、多くの開湯伝説の例に違わず、近世になってつくられた縁起であろうとの見方もある。
戦国時代には、大河ドラマ「真田丸」にも登場する豊臣方の武将、大谷吉継が湯治に訪れたことが、本人の手紙に書いてある。吉継はハンセン病者だったと言われており、演劇などでは、皮膚症状を隠す白頭巾姿で描かれることが多い。

草津のバスターミナルの3Fに2015年にオープンした、町立の「温泉図書館」。
湯畑を離れ、バスターミナルのビルにある草津町温泉図書館を訪ねた。2015年秋に町立図書館と温泉資料館が併合され、「温泉図書館」としてオープンした施設だ。その名のとおり、草津温泉の歴史にまつわる郷土資料が充実している。
同図書館の司書・中沢孝之さんは「草津温泉が全国的に有名になったのは、人々の往来が盛んになった江戸時代、文化文政期からです」と説明する。資料室には寛政年間に流行した「温泉番付」が貼ってあり、草津は東の大関に輝いている。当時はまだ横綱の格付けはなく、大関が最高位だ。
草津がこの時代に湯治場としてこれほどまで人気を集めたのは、霊泉のご利益が信仰を集めたからだ。湯畑の上手には薬師堂があり、薬師如来の足元から温泉が湧き出す位置関係にある。なかでも、湯畑の下手にあった滝の湯に打たれることで病が治ると人々は信じた。「温泉宿も、この点を積極的に宣伝していたようです」と中沢さん。
当時の湯畑の絵図は、いまでいうパンフレット。そこに描かれた薬師堂と湯畑の周辺の風景は、あたかも浄土の光景のようにも見える。この頃は、ハンセン病者向けの湯はあったものの、特に一般客との混浴が禁じられることはなかった。いにしえの草津は、病にかかわらず誰もが平等に薬師如来の加護を求めることのできる信仰の場だったのである。

明治12年に発行された「上州草津温泉之図」。中央に湯畑、そのうしろに、「日本温泉三大薬師」のひとつとされる草津山光泉寺が描かれている。

温泉図書館の司書、中沢孝之さんは、草津温泉の歴史とともに草津のハンセン病の歴史調査にも取り組んでいる。
草津に転機が訪れたのは、1869年(明治2年)のことだった。4月7日、温泉街を大火が襲った。中心部の全域を焼き尽くしたこの火事は、幕末から維新にかけての動乱で湯治客が激減していたまちの経済に、さらなる追い打ちをかけることとなった。
温泉宿の経営者たちは、復興策として湯治客の誘致に必死になり、効能の宣伝に力を注いだ。その結果、全国からハンセン病者が草津へと集まってきたのである。大火から10年後には、まちは賑わいを取り戻したという。ドイツ人医学者ベルツが、殺菌力の高い強酸性の草津の湯の有効性を発表すると、ハンセン病者を含む浴客がさらに押し寄せた。
ところが、草津温泉の知名度が上がり、外国人や有力者など一般の観光客が増えるにしたがって、次第にハンセン病者の存在が疎まれるようになっていく。まちの有力者らは温泉街の改良を名目に、ハンセン病者を湯之澤に集住させ、まちから追い出す計画を立てた。
患者らはこの案に反発し、交渉は難航。「そんな中、まちはハンセン病者に特に好まれた頼朝ゆかりの『御座の湯』の浴舎を取り壊してしまいます。その代わりに、湯之澤に湧く温泉を自由に使わせることなどを条件とし、患者たちに移住を承諾させたのです」(中沢さん)
こうして1888年に、患者とその家族、ハンセン病者専門の宿屋など30数名からなる湯之澤集落が誕生した。住人の希望により、当地の温泉は「御座の湯」と改称された。このとき、本来の御座の湯は「白旗の湯」の名を与えられ、今日に至る。ちなみに、湯之澤集落が解散しておよそ70年後にあたる2013年、湯畑のほとりに「御座之湯」が再現された。

かつての湯之澤集落。温泉街を「上町」、湯之澤を「下町」と呼んで区別されたが、住民や経済の行き来は活発だった。

「湯之澤」の地名を唯一残す、現在の「湯ノ沢橋」の欄干。
移住したハンセン病者たちは自らの力で荒れ地を開拓し、「自由療養村」の建設を目指した。当初は少数だった住人も少しずつ増え、「気兼ねなく湯治に専念できる」との理由で、草津の外から家をたたんで家族とともに越してくる患者も少なくなかった。資金のある者はまず、外から湯治に来る患者のための宿屋を開いた。それらの湯治宿が賑わい出すと、商店も増えていった。
湯之澤は設立当初から草津村の一集落として認められ、住人は納税などの義務と同時に居住権を得ていた。1900年に町制が敷かれて草津村が草津町になり、さらに区制が敷かれると、湯之澤は第五区として独立した行政単位を構成することとなった。郵便局や消防団を有し、草津町議会にも町会議員を送った。
「草津町で火事が起こったとき、真っ先に駆けつけたのが湯之澤の消防団だったと言います。きちんとした自治組織があり、町と協力しあう体制が整っていたのでしょう」(中沢さん)
草津の人々は、温泉街を「上町(うわまち)」、湯之澤を「下町(したまち)」と読んで区別した。とはいえ、両者のあいだの交流は失われることはなかったのである。集落の境には木戸門が設けられたものの、いつしか有名無実化していた。「上町の人たちが下町のカフェーでお茶を飲むこともあれば、両方の子どもたちが一緒に遊ぶこともありました」(中沢さん)
経済的な結びつきも強かった。上町の商人たちは湯之澤へ行商に通っていたし、集落の消費組合は上町から物品を仕入れていた。また、集落の労働者組織は上町の大旅館と契約し、雑事一切を請け負っていた。旅館にとって、観光客の目に触れない下働きの担い手であれば、ハンセン病者であることは関係なかったのかもしれない。
もちろん、病者を忌避する人もいただろうし、差別もあっただろう。それでも、中沢さんによれば、この当時、ハンセン病の集落とこうした地域ぐるみの交流をしていたケースは、国内はもちろん世界でも非常に珍しいという。ハンセン病の歴史に特筆されるものと言えそうだ。
中沢さんは、上町の住人たちが患者を嫌わなかった理由を「長年にわたり町の中心で湯治を行い、密に接してきた経験から、ハンセン病がうつることはないと知っていたからでしょう」と指摘する。ただし、文献などから当時の町民の感覚を読み取ることは困難であり、「今後も調査、研究が必要」と話す。
当時すでに、医学的にはこの病気が感染症であることは明らかになっていたが、草津町では遺伝病と誤解されていたようだ。そのくらい、この病気の感染力は低い。実際、湯之澤部落ができる以前、温泉街の宿屋は湯治で逗留する患者と寝食をともにしていたにもかかわらず、宿屋業者の家族で誰ひとりとしてハンセン病にかかった者はいなかったという。

聖バルナバ教会の堂内に飾られている、コンウォール・リー女史の肖像写真。

聖バルナバ教会と、併設された「リーかあさま記念館」(建物の左側)。

「頌徳公園」にあるリー女史の胸像。この一帯はかつてハンセン病患者救済のためにリー女史が所有していた土地。
中沢さんの案内で、湯之澤のあった辺りを歩いてみた。集落はすでに跡形もなく、冬場はスキー客で賑わう温泉旅館が点在しているばかりだ。わずかに、上町と下町の境にあった木戸門の門柱とおぼしき古ぼけた石の柱が2本、湯川にかかる橋のたもとに残っているのみである。
そこから西南の丘を上った上町のはずれに、「草津聖バルナバ教会」がある。湯之澤の歴史は、この教会を建てたイギリス人宣教師メアリ・ヘレナ・コンウォール・リーと、彼女の展開したハンセン病者の救済事業「聖バルナバ・ミッション」を抜きにしては語れない。取材チームは、教会に併設された「リーかあさま記念館」を訪ねた。
日本へ派遣され、東京の牛込聖バルナバ教会で伝道活動をしていたリー女史が草津へ定住したのは1916 年、58歳のときだった。指導者を求める信者会の強い希望に応えてのことである。湯之澤ではその3年前に、宣教師ハンナ・リデルによって熊本の回春病院から派遣された日本人司祭が伝道集会を開催。これをきっかけとして、信者会が結成されていた。
リー女史がミッションを開始するにあたり、湯之澤に最初に設立したのが聖バルナバ教会だ。バルナバとはキリストの使徒で、その名は「慰めの子」を意味する。リー女史はその後、私財を投じて男女別の「ホーム」を建て、信徒となった患者たちを住まわせた。また、病院や幼稚園、小学校、未感染児童(親は患者だが感染していない子ども)の養育施設も建設した。
湯之澤の人口が最大の約800人となった1930年の時点で、聖バルナバ教会の信徒は上町の住人も含めて約570人にのぼったという。リー女史は、信徒たちから親しみと尊敬を込めて「リーかあさま」と呼ばれた。彼女が最初に購入した土地で、当時の草津聖バルナバ教会の裏手にあった土地は、いまでは「コンウォール・リー頌徳公園」として整備されている。
だが、リー女史のこうした業績は、世の中にはあまり知られていなかった。湯之澤集落が解散して以降、次第に草津町の人々の記憶からすら薄れつつあった。現在の草津聖バルナバ教会の司祭である松浦信さんは、「集落の人たちが草津楽泉園へ移住して、語り継ぐ人がいなくなってしまった。また、教会としても表立ってミッションの歴史を検証することはできませんでした」と打ち明ける。すでに社会復帰を果たし、過去を明かされたくない信徒もいるからだ。
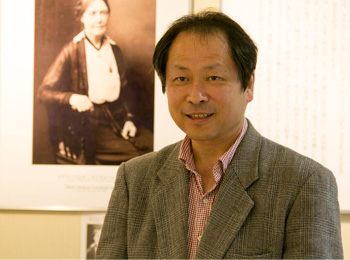
リー女史の偉業を伝える活動に取り組んでいる、聖バルナバ教会の司祭、松浦信さん
そんな中、2002年に草津町の有志によって「コンウォール・リー女史顕彰会」が結成された。メンバーのひとりで、記念館の案内人を務める内嶋貞夫さんは「リーさんのすごいところは、湯之澤だけでなく草津町の近代化にも貢献したところです」と話す。
例えば、草津で初めて幼児教育を手掛けたこともそのひとつ。湯之澤のほかに、一般の住人の住む上町にも幼稚園をつくった。また、教会や病院は、ハンセン病者ばかりでなく上町の人にも開放されていた。教会の近くに住んでいた内嶋さんの義父は、幼いころ、リー女史からクッキーを食べさせてもらった思い出があるという。
2016年の今年は、ちょうどリー女史がミッションを開始してから100周年になる節目の年。松浦さんと内嶋さんは「草津の歴史の貴重な側面として、リー女史が湯之澤で手がけた事業を研究し、伝えていきたい」と力を込めた。

湯之澤からの移住者たちが暮らした、栗生楽生園内の自由地区。家屋がまばらに残っているだけだが、いまもここで半自律的な暮らしを元気に営んでいる高齢の回復者たちがいる。

古びてはいるが、自由地区での平穏な暮らしぶりがうかがえる家。
取材チームは最後に、湯之澤からさらに東へ2キロほどの距離にある栗生楽泉園に向かった。ここには、全国の国立ハンセン病療養所の中で唯一、「自由地区」と呼ばれる特異なエリアをもつ施設だ。
1930年代になると国はハンセン病者の隔離政策を本格化させ、湯之澤のハンセン病者を収容するために栗生楽泉園を建設した。患者の中には、充実した医療を求めて自ら療養所へ入所する者もいたものの、多くは自由な生活が奪われることを恐れて移住に応じなかった。国としても、合法的に居住している「国民」をいきなり強制収容することはできなかったのである。
そこで国は、楽泉園の敷地内に自由地区を設け、資金のある者は一戸建ての家を建てて住んでよいこととした。湯之澤から家屋を移築することも認めた。人里から離れた場所とはいえ、これまでとほぼ変わらぬ自由な生活が約束されたのである。
こうして少しずつ移転が進み、最終的には県が移住を勧告して、1941年に湯之澤集落の解散が決定した。翌年末にはすべての住民が姿を消し、建物も取り壊されてしまった。
湯之澤から楽泉園へ移住したのは、当時の資料によれば合計で256人。そのうち75人が自由地区に入居した。国立療養所は患者の隔離を目的のひとつとする施設であり、外部との接触は厳しく禁じられていたが、全国でもここ楽泉園だけは例外だった。自由地区に限らず、患者や外部の人間の出入りが黙認されていたのだ。草津町の商人は、入所者の要望に応えて主に食料品や日用品などを売りに行った。
湯之澤が解散し、移転が完了するころには、次第に規制が強まっていたものの、それでも出入り商人たちは“もぐり”の営業を続け、園の職員もこれを見逃していたという。
それから70年以上――。現在も、楽泉園の自由地区に住み続けている入所者がいる。そのうちの何人かに話を聞くことができた。ある女性の住む戸建て住宅は、以前の家主が湯之澤から移築したものだという。自由地区では、ハンセン病の障害で日常生活に支障をきたす場合、患者同士で同居して世話をしてもらうことが認められていた。
彼女は目の不自由な家主を住み込みで看護し、家主夫婦が亡くなった後は夫とふたりでその家に住んだ。その夫もすでに亡くなり、いまは同じ家にひとりで静かに暮らしている。看護で得たささやかな収入を貯めて、日本各地を旅行したという。
隔離政策下にも楽泉園の入所者たちが一定の自由を確保できたのは、まぎれもなく60年に及ぶ湯之澤の実績があったからなのである。

写真左)リー女史の遺品とともにその業績を紹介する「リーかあさま記念館」 写真右上)栗生楽泉園の「自由地区」(「社会交流会館」に展示されている模型より) 写真右下)「リーかあさま記念館」で語り部をつとめる内嶋貞夫さんは、元楽泉園職員でもある。
参考文献:
栗生楽泉園入所者自治会『風雪の紋――栗生楽泉園患者50年史』(1982年)
廣川和花著『病者にとっての「生きていく場所」』(工作舎『ハンセン病【日本と世界】』2016年)
中村茂著『草津「喜びの谷」の物語ーコンウォール・リーとハンセン病』(教文館キリスト教書部 2007年)
中沢蔀著『草津の寺社仏閣』(群馬報知新聞社 1985年)
取材・執筆:三上美絵 写真:川本聖哉・長津孝輔