ハンセン病制圧活動サイト Global Campaign for Leprosy Elimination
People / ハンセン病に向き合う人びと

大阪府西淀川区。中島川と神崎川に挟まれた中州に
かつて「外島保養院」と呼ばれた療養所があった。
600名近くの患者が日々の暮らしをいとなんでいた。
だが、そのささやかな暮らしと患者の命は、
室戸台風の水害によって濁流のなかへと飲み込まれていく。
ここでは1909(明治42)年に建てられた公立療養所のうち、
唯一現存していない「外島保養院」の歴史をたどってみたい。
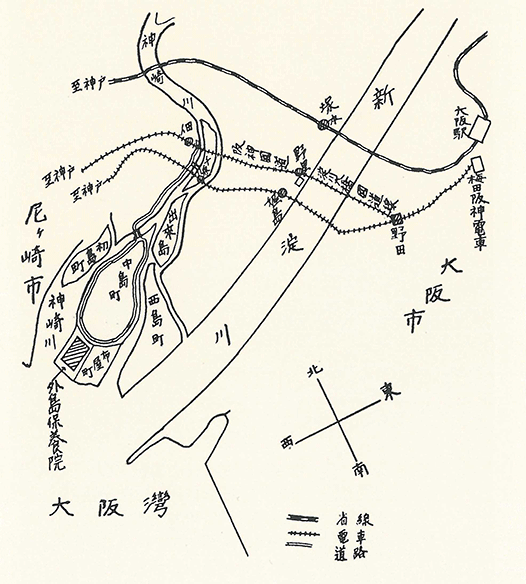
各地の反対運動により「第3区連合府県立療養所」は神崎川河口付近の海抜ゼロメートルの中州につくられることになった。これがのちに悲劇を生む原因となる
外島保養院は1907(明治40)年「癩予防ニ関スル件(法律第11号)」の公布にともない全国5ヵ所に初めてつくられた公立療養所のひとつである。開設はいずれも1909(明治42)年。第1区・全生病院(現・多磨全生園)、第2区・北部保養院(現・松丘保養園)、第3区・外島保養院、第4区・大島療養所(現・大島青松園)、第5区・九州療養所(現・菊池恵楓園)というのが、その全容だった。外島保養院の正式名称は「第3区連合府県立療養所」といい、2府10県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、三重県、岐阜県、福井県、石川県、富山県、鳥取県)の合同療養所という位置づけである。
外島保養院は当初、大阪府三島郡高槻町(現在の高槻市周辺)につくるという案があった。このとき敷地選定をおこなったのは大阪府衛生課だが、最終的に出された結論は当初予定していた高槻町ではなく、尼崎郊外の外島に療養所を建設するというものであった。選定に関わった当時の府立大阪医科大学学長・佐多愛彦の評伝、『佐多愛彦先生伝』(1940年刊)に次のような記述がある。
「当時先生は、大阪府技師の職を兼ねていたので、癩療養所の敷地選定に関与し、天野府衛生課長と共に三島郡高槻町の山手方面を物色したが、思わしからず、転じて尼ヶ崎郊外の外島村を選定して買収を決定し、その設計に着手して四十二年(※註:明治42年)三月竣工、四月一日開院の運びとなった」
外島は神崎川の河口で大阪湾に面し、海と川に囲まれた中州で、療養所が建てられた当時は周囲2㎞四方に民家すらなかったという。それもそのはずで、この土地は1908(明治41)年以前には名前すらつけられていなかった。療養所の建設に合わせ、1908年11月に西成郡川北村字布屋町の一部を急遽、外島と改称したのである。
海抜ゼロメートルの湿地帯。そこは文字どおり人の住まない「捨てられた土地」だった。当初予定された高槻町を「思わしからず」という一言で退け、なぜこの地に療養所を開設したのか。その真相はいまだよくわからないが、この決定がのちに大きな悲劇を生む起点となったことは確かだ。敷地面積は2万坪、開設当初の定員は300名であった。

昭和初期の入所者居住区の様子。院内には真水の出る井戸がなく、飲料水の確保にも苦労した。電灯線が引かれたのは、ようやく大正末期になってからだった
開設当時の外島保養院は敷地の40%が事務本館、医官室、職員住宅などの官舎地帯、30%が入所者の住宅、残り30%が農地となっていた。官舎地帯と患者地帯は他の療養所同様、厳重に区切られており、患者たちが官舎地帯を越えて正門へ行くことは許されなかった。一方、裏門には守衛がいて患者が脱走しないか、つねに目を光らせていたという。衣類は男女、年齢を問わず同じ縦縞の筒袖で、縞馬(シマウマ)と揶揄された。
食事は当初、食材を現物支給して各自に自炊させる方式をとっていたが、1928(昭和3)年からは職員による共同炊事にあらためられた。主食は米3合5勺に麦が2合。量は十分だったが、米は外米で内地米のような粘りはなく、独特のにおいがあり、慣れないうちは喉を通らない人も多かった。1人分の食費は1日あたり13銭前後で副食は味噌、醤油、だしじゃこ、漬物、院内産の野菜がせいぜい。タンパク質はほとんど摂ることができなかった。
外島保養院では、いくら井戸を掘っても塩分を多く含んだ水しか出なかったため、神崎川を4㎞ほどさかのぼり、川の水を船で運んで飲料水とした。そのままでは飲料には適さないので、濾過したものを配水したという。四方を水で囲まれていながら飲料水に不自由するとは、なんとも皮肉な話だ。
電気に関しては開設当初から自家発電設備こそあったものの、あかりはかすかなものだった。患者の暮らす大部屋27畳に対し、明かりは6燭(蝋燭6本分)の電球がひとつだけ。上水道、電灯線が引かれたのは外島が大阪市に編入された1925(大正14)年以降になってのことである。

1926(昭和元)年に定員1千人規模を目指して移転計画が発表されたが、各地で激しい反対運動が起こり移転が実現することはなかった。写真は外島保養院正門の風景
1920(大正9)年、内務省は「患者1万人収容」を目標に掲げ、合わせて公立療養所の増床および拡張、国立療養所の新設を決定した。外島保養院に対しても「定員1千人規模の療養所として拡張すべし」という方針が示されたが、海抜ゼロメートルの湿地に開設時の3倍以上にあたる1千人規模の患者を収容するのは、さすがに無理がある──。そう考えたのか、政府は1926(大正15)年1月7日、大阪府旧泉北郡北上神(きたにわ)村と美木多(みきた)村にまたがる地域(現在の堺市南区赤坂台付近)に療養所を設置する、という措置命令を通達した。
この措置命令を受けて大阪府は6万坪の予定地のうち、ひとまず2万坪を買収。残る4万坪については、土地収用法によって強行収用することになっていたという。この状況を見るかぎり国と大阪府の間で、この話はかなり以前から動いていたとみるべきだろう。この措置命令は大阪府知事を通じて公報という形で下達された。
これに対して旧泉北郡では町村長が団結して移転反対運動を展開。同年2月5日に開催された泉北郡民大会では、「官憲の反省をうながし、療養所の建設計画を撤回すること」「抗議が受け入れられない場合、泉北郡の町村長は全員総辞職する」「目的を達するまで(=建設計画が撤回となるまで)後任を選ぶための選挙もおこなわない」などの決議を採択した。郡民大会につめかけた民衆は4000人以上、これに対して会場内を監視する警察官は60名ほどであったという。
閉会にあたり壇上に上がった代議士が「当局の取り締まりが不穏当であったと信じる」と述べて警察に検束されると、場内は大乱闘となった。このときの騒乱で検束された者10数名。さらに大会終了後、所管の警察署でも衝突があり、ここでも検束者8名、警察側の負傷者5名を出した。警察側は抗議の中心人物に対し、治安維持法を適用するつもりである、と通告したという。治安維持法は前年の1925(大正14)年に制定されたばかりだった。
外島保養院の移転問題は翌週になって中央議会でも取り上げられたが、内務省は質問に対し予定地は不適当な場所ではない、建設地点は変更しない、泉北郡民大会での衝突は不当な言論弾圧ではない、と繰り返すにとどまった。
「外島保養院の歴史をのこす会」編纂による冊子『大阪にあったハンセン病療養所 ──外島保養院 2017年2月 大阪市保健所感染症対策課発行』には、療養所移転反対運動はいったん沈静化したと記述されているが、これは1926(大正15)年12月25日に大正天皇が崩御したことも大いに影響したと思われる。翌年の1927年に入ると反対運動はふたたび再燃した。

邑久光明園では前身である外島保養院の歴史を後世に残すため、歴史証言、手記、写真などの収集を独自に進めてきた。長年自治会長を務めた望月拓郎さん(写真手前)もそのひとり
外島保養院では収容人数を増やすための増築が順次おこなわれていた。増築は都合2回実施されており、1回目の1915(大正4)年に4棟を増築して定員は100名増の400名、2回目の1928(昭和3)年には6棟が竣工して定員は550名となっている。1915年は大正天皇、1928年は昭和天皇の、それぞれ御大典(即位のための式典)があった年である。
外島保養院の増築工事は京都御所でおこなわれる即位の礼に合わせ、京阪神地方の浮浪患者を収容するという狙いがあった。しかし、それでも1924(大正13)年に内務省が目標として掲げた「定床1千名」には遠く及ばない。旧泉北郡への移転は激しい反対運動など紆余曲折の末、1928年夏に撤回された。これを受けて内務省は外島保養院周辺の土地を埋め立て・拡張して「定床1千名」を実現する計画を発表。しかし今度は外島周辺の西淀川区、尼崎市などで激しい反対運動が巻き起こる結果となった。
対応に苦慮した大阪府は兵庫県淡路島の沼島、高知県甲浦(かんのうら)町生見(現・東洋町)、さらに瀬戸内海の孤島など移転計画全18案を立案・模索したものの、すべてが頓挫。内務大臣は「やむをえず現在の場所に拡張することになった。地域住民に迷惑をかけないように十分留意する」と発表、外島埋め立て計画断行が決まった。内務大臣発言を受けて帰阪した大阪府議らが反対派説得にまわり、運動はやむなく打ち切られることになったという。
外島保養院の拡張工事が開始されたのは1932(昭和7)年5月。4万坪の埋め立て工事が完成し次第、即時増築作業にかかるというのが計画の骨子で、内務省の掲げた「定床1千名」は、順調にいけば1934(昭和9)年の年末に実現される見通しだった。

桜井方策著『旧外島保養院誌』。機関誌「楓」の抜き刷りを製本したもので数冊しかつくられなかった。外島保養院の様子をいまに伝える貴重な資料である

他の療養所同様、外島保養院でも野球の試合がさかんにおこなわれた。写真は昭和初期の院内リーグ戦開会式の様子。村田院長赴任後には長島、大島への遠征なども実現した
邑久光明園に『旧外島保養院誌(以下、保養院誌)』という本が所蔵されている。著者は桜井方策といい、外島保養院の初代医長を務めた人物だ。内容は外島時代にあった事件、エピソード、人物評などバラエティに富んでおり、語り口はどことなく講談の冒険譚のようでもある。もともとは機関誌「楓」に連載記事として掲載されたもので、原稿を依頼したのは「楓」編集部の望月拓郎さん(邑久光明園・元自治会長)だった。
外島保養院は患者自治がはやくからおこなわれたことでも知られるが、それは1927(昭和2)年に赴任した村田正太(まさたか)院長の指導方針によるところ大であったと言われている。村田院長は守衛、見張り、鉄条網の撤廃を始め、数々の改革を断行するとともに、識字学級、小中学校など教育のための学校も開設。俳句、短歌、詩などの文芸もさかんになり、講師を呼んでの指導、月刊誌の出版などもおこなわれた。1931(昭和6)年に「外島タイムス(自治会教育部編集・発行)」が創刊されたのも、こうした背景があってのことだ。内容は自治会広報、小論文、ニュース、短文芸など多岐に渡っていた。
院内では1923(大正12)年頃から軟式野球が始められ、寮舎を東西にわけての対抗戦、職員チームとの試合などがおこなわれていたが、1932(昭和7)年に長島愛生園との交流試合がはじめて実現。3月におこなわれた外島での試合では保養院チームが圧倒的勝利をおさめ、7月に遠征した長島(岡山県)でも10対1のスコアで大勝。翌日おこなわれた大島療養所での試合でも、23対22という大乱打戦を制して外島チームが勝利した。
院内の待遇も改善された。食事内容が大幅によくなったほか、充分な小遣いも出た。衣類や下駄の花緒も男女別々の柄となり、羽織も支給されたという。一時帰省も認められたが、これも当時としては画期的なことだった。このような改革が断行できたのは当時の療養所が内務省(※警察、財務、土木、衛生などを担う有力官庁)管轄であったことも大きく影響していたと思われるが、園長がもつ権力は絶大で、患者の待遇は園長の方針次第というところがあった。
また村田院長はエスペラント語(※19世紀末につくり出された世界共通語)の普及運動などもおこなったという。患者たちは内外のさまざまな思想にも親しむようになったが、これがのちに「外島事件」と呼ばれる騒動につながる遠因となった。
『保養院誌』によると、大阪府警察部はかねてより外島保養院のことを「赤化分子(※共産主義者のこと)がおる。そして同所を赤化先鋭化させようと着々手をつけている」と見ていたという。最初の取り調べがおこなわれたのは1933(昭和8)年8月初旬で、大阪府警察は所管の大和田警察に命じて職員4名(書記、タイピストの女性、看護婦長代理、看護婦)を拘引、そのまま帰さなかった。村田院長であれば職員を黙って引き渡すことはなかったと思われるが、この日は熊本へ出張中で不在。明らかに院長不在を狙っての捜査であった。8月27日の大阪毎日新聞には「レプラ患者に“赤の媚薬” 大阪外島保養院書記ら留置して取り調べ」の文字が躍った。いわゆる「外島事件」のはじまりである。

急進派と呼ばれた20名を退去させるにあたり、村田院長は送別会を催し各自にそれぞれ風呂敷包みと餞別を手渡した。壇上には「父」「慈」「送」などの文字があり、過激分子として追放したのではないことが見てとれる
新聞での報道を受け、外島保養院内では多数を占める保守派(穏健派)と急進的思想をもった革新派の対立が激化。保守派患者らは「過激な急進派を院外に放逐しなければ保養院の安穏は望めない」として、急進派患者の追放を村田院長にせまった。そして8月29日夜、村田院長はついに急進派患者20名を退去させることを決定。翌30日夜には自動車で4人ずつ阪神国道筋まで送っていった。このとき村田院長は風呂敷包みのほか、餞別としてひとり10円を手渡したという。
この件は新聞によって「患者脱走事件」として報道された。1933(昭和8)年9月3日付大阪毎日の紙面には「左翼患者廿(※二十)名 夜陰保養院を脱走す 堤防を越えて大阪市内外へ潜入 奇怪! 院長の許可を得て」とあり、大阪朝日も「癩患者二十名 奇怪な療養所脱出! 軋轢に手を焼き院長が退去を黙認」と報じている。こうした報道は連日にわたって繰り返された。
村田院長も大阪府警察部による事情聴取を受けたが、このとき府警察は外島保養院の会計にも疑問な点があるとして、同院の会計調査もおこなっている。どんな組織も叩けば埃が出ると思ったのか、それとも事前に内偵があったのか、真相はわからないが、この一件によって村田院長と大阪府警察部、大阪府衛生課との対立は決定的なものとなった。
大阪府衛生課の国澤課長は村田院長と同じ高知県出身、東京帝国大医学部の先輩。大阪府警察部長の粟屋千吉は同年6月に起きた「ゴーストップ事件(※)」で陸軍大阪師団長とやり合った人物だった。一方、村田院長も「曲がったことがきらいで、こうと決めたら絶対に引かない」と言われた硬骨漢である。特高警察による村田院長の取り調べは延々50時間以上におよんだという。
(※大阪北区で信号無視をしようとした陸軍所属の一等兵が曾根崎警察の巡査に止められ、同署に連行された事件。陸軍と警察・内務省の対立へと発展した)
最後は粟屋警察部長と村田院長の一騎打ちになるも双方相譲らず、ついには匕首まで持ち出す事態になった……とは『保養院誌』にあるエピソードだが、これがどこまで本当なのかは、著者の桜井方策氏のみぞ知る、といったところだろう。ちなみに粟屋警察部長は内村鑑三の薫陶を受けたクリスチャンで、後年1943年(昭和18)年に広島市長に着任、1945(昭和20)年8月15日の原爆投下で殉職している。
こうした一連の騒動に対して村田院長はどう思っていたのか。1933(昭和8)年10月3日、朝日新聞の記者に語ったことばが残されている。
「六万に達するわが国のらい患者のうち僅かその10分の1に当たる六千名より収容されていない現状で僅か20名の患者を外に出したら、あたかも大問題が勃発したかの如く騒ぎ立てた府当局の態度は専門家の目からすれば、全くお話にならない素人の馬鹿騒ぎである。(中略)自分の辞任云々については、まだはっきりしたことは申し上げかねる」
この取材を受けたあと村田院長は患者自治会に赴いて自治会役員に辞職の意向を伝えたという。院内礼拝堂で「決して諸君を見捨てるのではない、今後はらいの治療薬発見に一生を賭ける所存である」と挨拶した村田院長は、この年の10月10日、外島保養院をあとにした。翌年末の竣工をめざし、拡張埋め立て工事、増築作業が進むなかでの辞任であった。

入院者の命を救った堤防そばの大松。この松の巨木がなかったら、さらに多くの人が濁流にのまれていた

洪水被害のあとおこなわれた遺体の捜索活動

室戸台風のわずか5ヵ月前に外島へやってきた中野婦長。誠実な人柄で多くの入所者から尊敬され、慕われた
1934(昭和9)年9月21日未明、史上最大規模の「室戸台風」が高知県室戸岬付近に上陸。大阪を含む京阪神地方に大きな被害をもたらした。中心気圧911.9ヘクトパスカル、最大瞬間風速60メートル以上。外島保養院にも5メートル以上の高潮が押し寄せ、堤防が決壊。施設はほぼ全壊し、多くの患者が濁流にのまれ、命を失った。犠牲者は入所者597名のうち、約3割にあたる173名(男性107名、女性66名)。職員3名、職員家族11名、工事関係者9名を加えた死亡者数は196名にのぼった。西淀川区内の死者・行方不明者は248名であり、じつに8割近くが外島保養院の犠牲者だったことがわかる。
悲劇を生んだ最大の要因は、療養所にまったく適さない1級河川の河口、海抜ゼロメートル地帯に療養所を建てたことにあったが、移転計画が反対運動によって実現しなかったこともまた、大きな原因のひとつだったと言えるだろう。移転さえ実現していれば196名の命は失われずに済んだ可能性が高いのである。その意味で外島保養院壊滅は「室戸台風」と、患者を疎外し排除した社会、このふたつによってもたらされたと言えるのではないか。
保養院壊滅時に亡くなった196名のなかには患者たちから慕われた中野鹿尾(なかのしかお)婦長も含まれていた。京都の一燈園で修行したのち外島に就職した中野婦長はいつもやさしく、患者の履く下駄の花緒が切れているのを見るとポケットから細く切った布を取り出し、すばやく緒を立てたという。寮舎では中野婦長が巡回にきた、という声がかかると全員が脱ぎ散らかした下駄を揃えに出た。脱ぎっぱなしの下駄を中野婦長がすべて揃えてまわると皆が知っていたからだ。
室戸台風上陸当日、中野婦長は早朝から重病者棟へ向かい、津波がせまるなか必死で患者救助をおこなった。3往復目、病人を背負い、視覚障がい者の手を引いて堤防に上がろうとしたとき、やってきた高波にのまれたという。中野婦長が保養院に赴任したのは室戸台風からわずか5ヵ月前の4月。「婦長」任命は殉職によるもので、災害があったときの肩書きは看護婦だった。邑久光明園に「中野婦長殉職碑」が建てられたのは1942(昭和17)年9月のことである。
外島保養院で室戸台風被害に遭った藤本としさんは、のちに著書『地面の底が抜けたんです ──ある女性の知恵の七十三年史』で被災の様子を次のように書いている。
「翌日は神崎川の上流にテントが貼られて、ともかく身を横たえることができたが、草原に敷かれた布団は一人一枚の米俵、さんだわらは枕であった。ほかに、どこの救護品であったのか綿毛布が一枚与えられたが、まだ体も着物も海水に湿っているので、なんとも寒くて仕方がなかった。しかし起きている気力もないので、さんだわらに頭をのせていると、蟻がぞろぞろ這い上がってくる、バッタが飛びつく、こおろぎがところきらわず蹴っていく」
「眠りもできず、起きもかなわず、もうろうとしている空間に、目の前で溺れた友の顔が浮かび、その瞬間の絶叫が尾を引く。ごうごうとひびく濁流……、その中で白バラがゆれていた」

外島保養院跡地に建てられた記念碑。毎年9月の最終金曜日には関係者が集まって慰霊祭がおこなわれている
濁流のなかで揺れる白バラは外島保養院の堤を覆っていた蔓バラである。毎年夏になると直径4㎝ほどの白い花をつけた。藤本さんは夜明けとともに起き、朝露に濡れる壁一面の白バラを飽かず眺めたという。友を飲み込んだ濁流のなかにその花が揺れている、という描写は美しくはあるが悽愴で、なんともやりきれない。
外島保養院の生存者は424名。のちに1名が死亡、7名が退院したが、残りの416名は全国6ヵ所の療養所に分散委託されることになった。岡山県邑久郡(現・瀬戸内市)邑久町に「光明園」が開園するのは、室戸台風襲来から4年近くを経た1938(昭和13)年のことである。
現在、外島保養院があった場所には近代的な堤防が築かれ、周囲には巨大な物流倉庫が建ち並んでいる。堤防沿いにはスチール製のフェンスが巡らされているが、よく見るとその一角にひっそりと石碑が建っていることに気づくはずだ。細かな字で由来が刻まれた石碑の上には「外島保養院記念碑」の文字が並んでいる。建立は1997(平成9)年11月。海抜ゼロメートル地帯にあった療養所を偲ぶ縁(よすが)は、今ではこの石碑しかない。
毎年9月最終金曜日には、邑久光明園と邑久光明園入所者自治会主催による慰霊祭がとりおこなわれている。1934年9月21日は金曜日だったのだ。
参考文献:
外島保養院の歴史をのこす会 『大阪にあったハンセン病療養所 ──外島保養院』(大阪市保健所感染症対策課発行)
桜井方策 『旧外島保養院誌』(邑久光明園)
藤本とし 『地面の底が抜けたんです ──ある女性の知恵の七十三年史』(思想の科学社)
邑久光明園入園者自治会 『邑久光明園自治会80周年記念誌 邑久光明園入園者八十年の歩み 風と海のなか』(日本文教出版)
邑久光明園入園者自治会 『邑久光明園創立百周年記念誌 隔離から解放へ 邑久光明園入所者百年の歩み』(山陽新聞社)
※本稿に掲載した外島に関する図版、写真は光明園自治会の許可を得て『邑久光明園創立百周年記念誌』より転載させていただきました。
本サイトからの無断掲載はご遠慮ください。
取材・編集:三浦博史